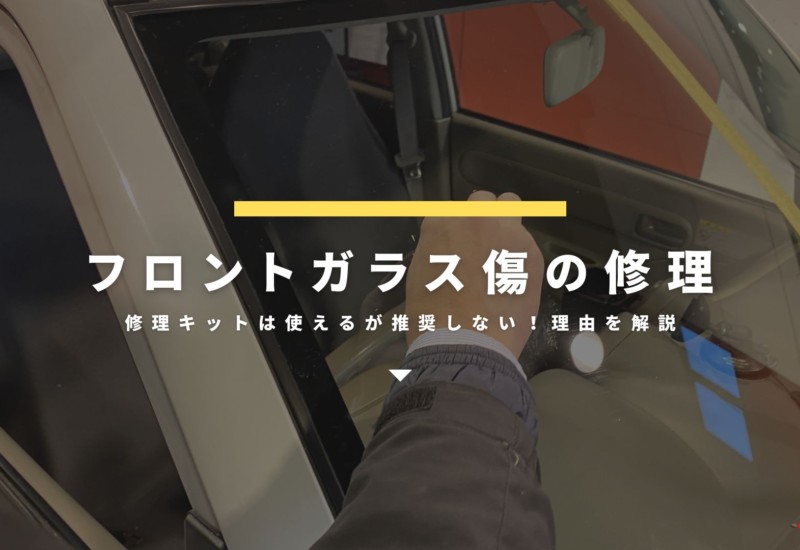車酔い・乗り物酔いの原因と対処法|乗り物酔いにおすすめの食べ物、飲み物も解説

連休や行楽シーズンになると、旅行やドライブに出かける機会が多くなります。
忙しさや日常生活から離れて、どんなところに行こうか計画を立てるのは楽しいものです。しかし、乗り物酔い・車酔いをしやすい人にとって、長時間のドライブは心配の種です。
そのため、車酔いを抑える事前準備を知っておけば、長時間の車移動であっても安心して旅行やドライブを楽しむことができます。
この記事では、車酔い・乗り物酔いが起こるメカニズムや原因、事前準備などについて解説していきます。
目次
車酔い・乗り物酔いが起こる身体のメカニズム
車・電車・飛行機・船などの乗り物酔いは、医療用語で「動揺病」「加速度病」と呼ばれています。乗り物酔いは「動揺」と「加速度」によって起こる現象です。
車酔い・乗り物酔いが起こるのは、以下のメカニズムが挙げられます。
車酔いは、同乗者によく起こる現象です。運転手は自分でハンドル操作をして、路面の状態から揺れを予測できます。
目から入ってくる情報から三半規管で感じる状況を予測できるので、車酔いが起こりにくいのです。
車酔い・乗り物酔いの原因は、体調不良や車内でのスマホ操作など
車酔い・乗り物酔いの原因は、以下の4つです。
- 体調不良
- 車内でのスマホ・ゲーム・読書
- 運転が雑、または荒い
- 道路の状態があまり良くない
体調不良
風邪を引いていたり熱があったり、疲労や睡眠不足などのコンディション不良があったりすると、車酔いが起きやすくなります。
また、食べ過ぎや極度の空腹時にも車酔いが起きやすいので、長時間のドライブになる場合は必ず体調を万全にしておきましょう。
以下のような症状をお持ちの人は、乗り物酔いをしやすいと言われています。
- 自律神経失調症
- 低血圧
- 喘息やアレルギー持ち
これらの症状を感じる人は、一度医師に相談してみてください。
車内でのスマホ・ゲーム・読書
車内では自由に過ごすことができるので、ゲームや読書をする人も多いです。ゲームや読書は独特な眼球の使い方をするので、目を長時間使った集中力を要する作業になります。
走行時の大きな振動の中でこのような作業を行うと、平衡感覚が狂ってしまい車酔いを起こしやすくなります。車内でゲームや読書をする場合は、こまめに休憩をとるようにしてください。
また、カーナビや位置確認のためにスマホを使うことも多くありますが、SNSや動画を車内で長時間見続けることも、同じように車酔いしやすくなる原因のひとつです。
運転が雑、または荒い
スピードの出し過ぎや急カーブを勢いよく曲がると、車体が大きく揺れるだけでなく、遠心力によって体の反応が追いつかなくなります。
車酔いしやすい人はもちろん、普段ならあまり車酔いしない人でも体調に支障をきたすことがあります。
道路の状態があまり良くない
山道や工事中の砂利道など、車が頻繁に横揺れや縦揺れする場合でも、車酔いしやすくなります。
車体が大きく揺れ続けるような道の走行は、できれば避けるのが望ましいのです。しかし、道路は常に綺麗に整備されているわけではありません。そのため状態が良くない道路では、大きな振動を起こさないように、丁寧な運転を心がけてください。
車酔い・乗り物酔いしやすい人の特徴は、体質や年齢など
車酔い・乗り物酔いしやすい原因以外に、車酔い・乗り物酔いしやすい人の特徴としては以下の3つが挙げられます。
- 体質
- 子供
- 精神的・心理的要因
体質
たとえばガソリンのニオイが苦手であったり、車独特のニオイが苦手であったり、嗅覚がとても優れている人は車酔いが起きやすいです。
車内にはタバコ、汗、食べ物など、様々な匂いが混在するので、車の揺れや景色の移り変わりの速さと合わせて、ニオイが車酔いを誘発することもあります。
子供
多くの人は年齢を重ねていくうちに、乗り物に乗る体験も重ねていき、身体の成長とともに、乗り物のスピードや揺れに慣れていきます。
小学校入学〜中学生までは、成人に比べて乗り物に慣れていないため、車酔いが起きやすいです。
三半規管が弱いなどの乗り物に酔いやすい体質になっていくのも、子供の頃の経験が大きく関係します。
また「起立性調節障害」を持つ子供は、乗り物酔いしやすいと言われています。
出典:社会福祉法人・恩賜財団済生会|子どもに起こりやすい起立性調節障害
精神的・心理的要因
頻繁に乗り物酔いを起こすことで、乗り物への強い不安感を抱えている人は、乗り物酔いになりやすくなっています。
また、その他にも普段から精神的なストレスを抱えている人は、乗り物酔いになりやすいです。
車酔い・乗り物酔いに即効性のある治し方はない!事前準備が大切
乗り物酔いになったら、すぐに体調を回復するのは難しいです。仮に乗り物酔いが起きたら、ゆっくりと体調を整えてください。
乗り物酔いに関しては、事前の準備が大切です。
こちらでは、車酔い・乗り物酔いを抑える事前の対処法、車酔い・乗り物酔いを起こした後の対処法について解説していきます。
車酔い・乗り物酔いを抑える事前の対処法
乗り物酔いをしないように、車に乗る前と乗車直後は以下のことを心がけてください。
- 長時間ドライブをする前夜は十分に睡眠をとる
- 車に乗る1時間前には食事を済ませる
- 酔い止め薬を飲む
- 走行中は遠くの景色を見たり下を見たりして、スマホはできるだけ見ない
乗り物酔いをしないためには、体調を整えることが大切です。
お腹の状態は満腹でも空腹でも良くないので、車に乗る1時間前には食事を済ませましょう。脂っこい食べ物や乳製品は避けて、胃に優しい物を食べてください。
車酔い・乗り物酔いを起こした後の対処法

もしも車酔い・乗り物酔いを起こした場合は、以下の方法で対処してください。
- 車から降り、こまめに休憩をして新鮮な空気を吸う
- 乗り物酔いに効く「ツボ」を押す
- 衣服を緩ませる
- 座席を寝かせて体を楽にし、頭部が揺れないようにする
以上のことを意識すれば、乗り物酔いの症状をやわらげることができます。
車酔い・乗り物酔いに効果的な手足のツボ5つ
車酔い・乗り物酔いの症状を和らげたり、乗り物酔いを予防したりするためには、内耳や自律神経に関連するツボを押すと効果が期待できます。
車酔い・乗り物酔いに、効果的なツボは以下の5つです。
| ツボ | 箇所 | 効果 |
|---|---|---|
| 翳風 (えいふう) | 耳たぶの裏の、耳たぶと骨のでっぱりの間にあるくぼみ | 平衡感覚をつかさどる部分全般に効くとされ、乗り物酔いの予防効果が期待できます |
| 侠谿 (きょうけい) | 足の薬指と小指の付け根の間の、薬指寄りの凹んだ部分 | めまいや頭痛、耳鳴りなどに効果が期待できます |
| 築賓 (ちくひん) | 足の内側のくるぶしから、膝の方へ向かって指5本分のところ | 不快感、嘔吐感、などに効果が期待できます |
| 外関 (がいかん) | 手のひらを下に向けた状態で、手の甲と手首の境目にあるしわの真ん中から指3本分ひじ側のところ(内関の反対側) | 自律神経を整える作用、疲労回復や頭痛改善に効果が期待できます |
| 内関 (ないかん) | 手のひらを上に向けた状態で、手と手首の境目にあるしわの真ん中から指3本分ひじ側へ進んだところ | 平衡感覚を正常にする、胃の不快感や吐き気を和らげる、二日酔い改善に効果が期待できます |
車酔い・乗り物酔いにおすすめの食べ物・飲み物
こちらでは、車酔い・乗り物酔いにおすすめの食べ物・飲み物について解説していきます。
車酔い・乗り物酔いにおすすめの食べ物は、チョコレートや梅干しなど
車酔い・乗り物酔いに、おすすめの食べ物は以下の4つです。

- チョコレート
- ガム
- グミ
- 梅干し
チョコレートは血糖値を上げて、脳を目覚めさせてくれます。ガムやグミは、噛むことによる覚醒効果が、乗り物酔いの予防に繋がると言われています。
梅干しについては、食べると唾液がたくさん出るため、三半規管のバランス感覚を正常にして、乗り物酔いを解消してくれるとされています。
車酔い・乗り物酔いにおすすめの飲み物は、コーラや生姜系のドリンク
車酔い・乗り物酔いに、おすすめの飲み物は以下の4つです。
- コーラ
- ペパーミントティー
- 生姜のハチミツ漬け
- 紅茶(すりおろした生姜を入れたもの)
- ハーブのジンジャーティー
- ミネラルウォーター
- スポーツドリンク
カフェインを含む炭酸水であるコーラは、乗り物酔いに効くと言われています。炭酸水は自律神経を整え、カフェインはリラックス作用があるため、乗り物酔いに効果的です。
ただし、カフェインには利尿作用を促す働きがあります。そのため、運転中はトイレが近くなる心配があるので、大量にコーラを飲むのは避けてください。
ペパーミントティーは胃の不快感を軽減する作用があり、生姜は吐き気を抑える効果があると言われています。
そのほかには、ミネラルウォーターやスポーツドリンクなど、胃に刺激の少ない飲み物もおすすめです。
車酔い・乗り物酔いに食べてはいけないもの、飲んではいけないもの
車酔い・乗り物酔いにおすすめしない食べ物・飲み物は、以下の3つです。
- 脂っこい食べ物
- 乳製品
- 柑橘系の食べ物や飲み物
これらの食べ物や飲み物は、胃に負担をかけたり胃の働きを活性化させたりするため、乗り物酔いを誘発しやすいです。
飲み物で言えば、オレンジジュースやレモンウォーターなどは気軽に飲みやすいですが、車や新幹線等に乗る際はやめておきましょう。
車酔い・乗り物酔いで嘔吐したときの対処法
同乗者に車酔いの人がいる場合は、万が一のことを考えてビニール袋を持っておいてください。
嘔吐物がシートに飛び散ったときのことを考えて、水拭き・乾拭き用に雑巾やタオルを3枚ほど、除菌シートを用意しておきましょう。
嘔吐物がシートに飛び散って、ニオイや汚れを取り切れない場合は、プロにクリーニングを相談してください。
翌日も乗り物酔いが治らない、嘔吐を何度も繰り返す場合は医師に相談を
翌日になっても乗り物酔いの症状が収まらない、また嘔吐を何度も繰り返すほどの症状が出る人は、医師に相談してみてください。
乗り物酔いには脳と内耳が深く関係しているため、脳に障害があったり内耳に機能障害があったりするかもしれません。
たとえば自律神経失調症の人、喘息やアレルギーをお持ちの人は、乗り物酔いをしやすいと言われています。
そのため、翌日になっても乗り物酔いの症状が収まらない人、また20歳を過ぎても乗り物酔いを克服できない人は、一度医師の診察を受けましょう。
車酔い・乗り物酔いについてのまとめ
- 車酔い・乗り物酔いが起こる原因は、体調不良であったり体質であったりする
- 車酔い・乗り物酔いは即効で治らないので、事前の準備が大切
- 食べ物や飲み物は胃に優しいものを選び、乳製品や柑橘系のものは避ける
乗り物酔いは、平衡感覚を司る三半規管に異常が起きることによって発生する、自律神経失調のひとつです。
車酔いが起こりやすい人は、酔い止め薬を飲みましょう。ただし副作用もあるので、酔い止め薬を購入する際に気になる症状があれば、薬剤師さんに相談してきちんと処方してください。
この記事の監修者
![]()
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。