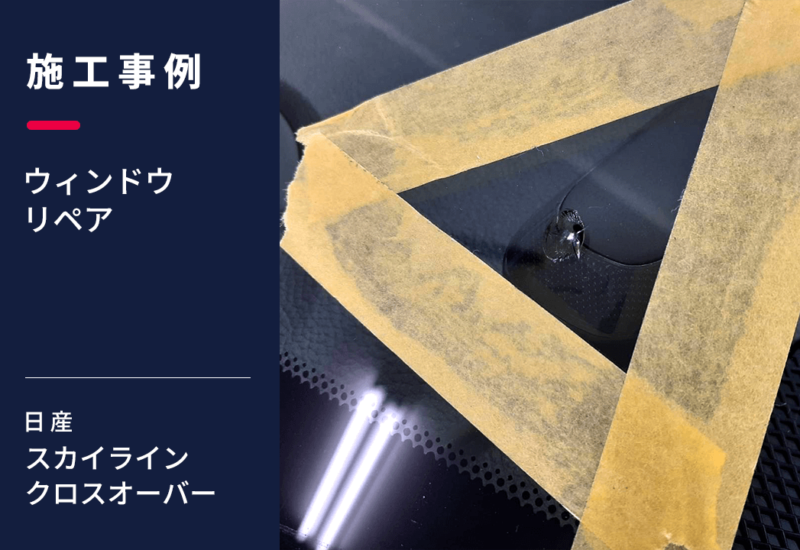融雪剤で車や人体に影響がでる?融雪剤で錆びないための洗車の方法・頻度を解説
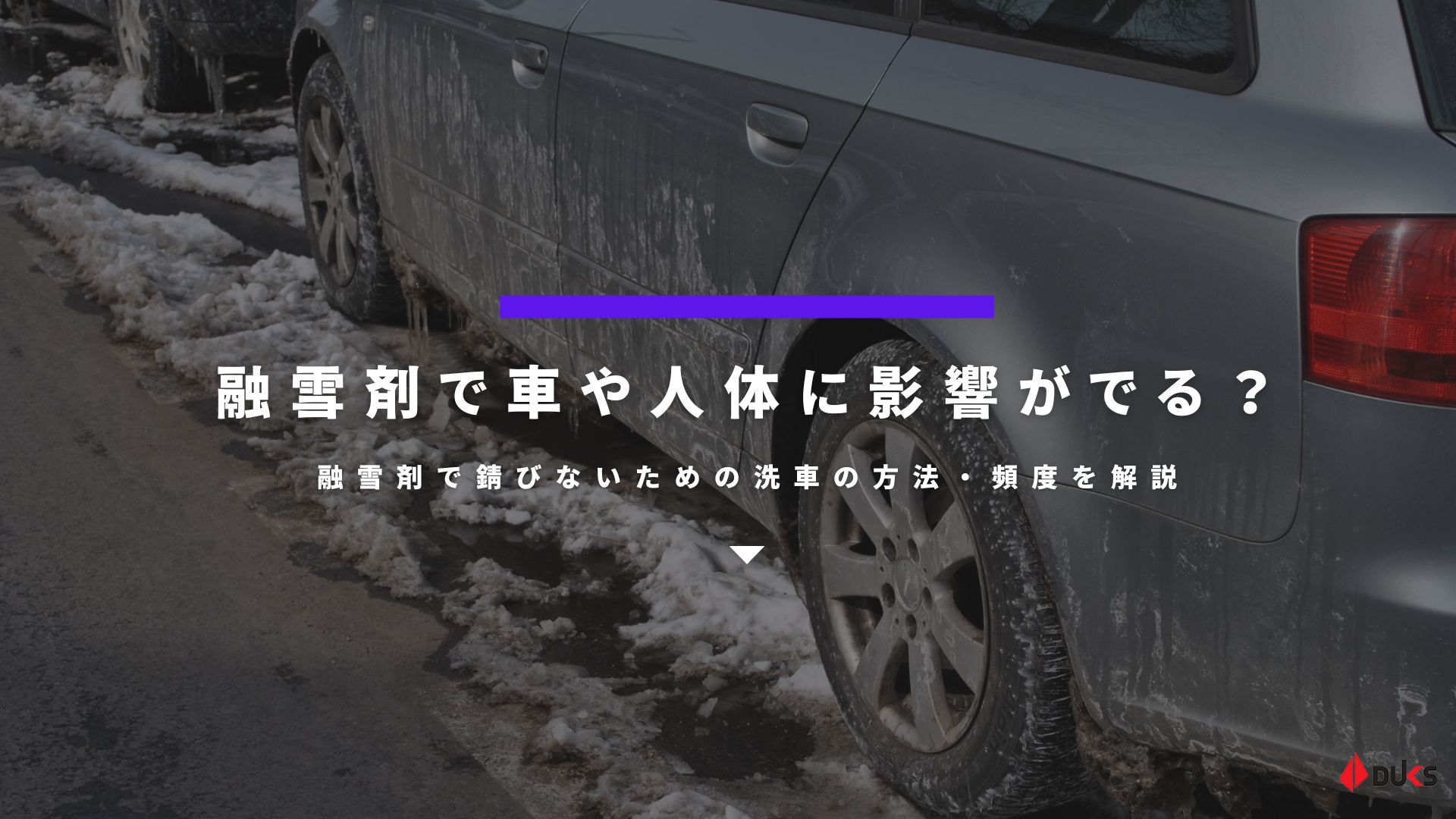
融雪剤で車が錆びないためには、洗車の方法や頻度、そして適切なコーティングが欠かせません。
冬季に道路へ散布される融雪剤は、雪を溶かす効果がある一方で、塩分を含むため自動車の下回りに付着すると金属を腐食させ、錆びる原因になります。
特にフレームやサスペンションなどは影響を受けやすく、放置すれば故障につながる恐れがあります。
今回の記事では、融雪剤の成分や働き、車体への影響、洗車のタイミングと方法、下回りのコーティング施工について解説していきます。
目次
融雪剤とは?
融雪剤とは、雪を溶かしたり凍結防止効果があったりする塩分です。こちらでは融雪剤の効果と成分、融雪剤はなぜ溶けるのかについて解説していきます。
融雪剤の効果と成分
融雪剤とは雪の降りやすい寒冷地域で使用されており、車を凍結から守ります。たとえば、冬の高速道路の路面を覆っている白い粒が融雪剤です。
また積雪する地域では車を出すために、自分で駐車場に融雪剤を使用することがあります。
融雪剤の効果や成分は、以下の表にまとめたので参考にしてください。
| 融雪剤の効果 | 融雪剤の主な成分 |
|---|---|
| ・雪を溶かす ・凍結防止 | ・塩化ナトリウム ・塩化カルシウム ・塩化マグネシウム |
融雪剤はなぜ雪が溶けるのか?
融雪剤を撒くと、なぜ雪が溶けるのか?それは成分である、塩化カルシウムが関係してきます。塩化カルシウムが水に混ざると、0度では凍らなくなるため、今まで0度で凍っていた氷が溶けてしまうのです。
さらに塩化カルシウムは、水に溶ける際に発熱します。塩化カルシウムが水に溶けると、「塩素イオン」と「カルシウムイオン」に分かれて、水の中を動き回ります。この動きが熱になり、温度が上がって雪を溶かしてくれるのです。
融雪剤の疑問①車が錆びる?錆びない?

融雪剤の影響で、車が錆びる恐れがあります。また、最悪の場合は車が故障する可能性もあります。
車が錆びるリスクはある
融雪剤に含まれる塩化ナトリウムや塩化カルシウム、塩化マグネシウムには、金属の腐食を促進させる塩分が含まれています。
しかし、これらの成分のみでは車体が錆びることはありません。雨や雪、氷など空気中の水分と化合して金属に付着し、酸化することによって錆びてしまうのです。
融雪剤の塩分を含んだ水分は蒸発しにくい性質をもち、金属をより酸化させやすくなります。
融雪剤に含まれている「塩」と「不純物を含んだ水分」が車の「鉄」に付着し、錆びてしまう仕組みです。
特に、車の足回り(シャシ)などは融雪剤の影響を受けやすい部分です。
冬季期間は常に新しい融雪剤が散布されているルートも少なくないので、影響を受け続ける期間が長くなり、錆のリスクも高まってしまいます。
冬の期間は、車の足回りをこまめにチェックし、きれいな状態を保つようにしてください。
最悪の場合は車が故障することも
路面に散布された融雪剤をタイヤが巻き上げ、エンジンルーム内に融雪剤が入り込んでしまうことがあります。
そうなると、エンジンの周辺装置(サスペンション、ブレーキ配管、ブレーキ周り、タイヤ、ホイールなど)に融雪剤が堆積してしまい、錆びが進行して故障に繋がってしまうのです。
融雪剤による錆びを放置した結果、車が廃車になってしまったケースも多くあるので、車体に付着した融雪剤の処理には気を配るようにしましょう。
融雪剤の疑問①融雪剤は人体への影響はある?
融雪剤は、人体に影響が出る可能性は否定できません。融雪剤に多く含まれる「塩化カルシウム」は、水に溶けると発熱するため、濡れた手や足につくと、皮膚炎などが起きる場合があります。
降雪地帯に住んでおり、自宅の敷地や駐車場に融雪剤を使う場合は、次の点を覚えておくと良いです。
- 錆びない融雪剤(無塩タイプ)を選ぶ
- マスク、メガネ、手袋を装着し、服装に気をつけて作業をする
- 自分の庭や駐車場の広さに合わせて、適量の融雪剤を撒く
現在では車が錆びないよう、無塩タイプの融雪剤が販売されています。無塩タイプの融雪剤の主成分は、カルボン酸、尿素などです。
塩分が入ったタイプとは違い、環境に優しく車が錆びりことがありません。ただし、融雪剤を家庭で使用する際は、マスク、メガネ、手袋、服装に気をつけて作業してください。
また、融雪剤はペットボトル1本(2リットル)で約30平方メートル、幅3メートルの道路なら10メートルの範囲に散布できます。
むやみやたらに撒くと、コンクリートや通行人に影響が出るリスクがあります。必要最低限の量だけ、融雪剤を散布するようにしてください。
車の洗い方|融雪剤で車が錆びないための洗車方法

こちらでは、融雪剤で車が錆びないための洗車方法について、自分で手洗いする場合と洗車機を使う場合で解説していきます。
手洗い洗車の場合
高圧洗浄機などを用いて、車全体に水をかけながら洗い流します。タイヤのホイールなどにも融雪剤が残りやすいので、入念に洗い流してください。
仕上げに、普段よりも多めのシャンプーを使って、融雪剤を完全に洗い落としてください。
洗車機を使う場合
洗車機の設定をする際に「下部洗浄」をオプション設定し、洗車を行ってください。
有料オプションであるため、通常の洗車オプションよりも若干費用はかかってしまいますが、融雪剤を確実に落とすためにはこの方法がとてもおすすめです。
全て自動で行ってくれるので、下部に付着した融雪剤を楽に落とすことができます。
融雪剤を拭き取る際の注意点
融雪剤を拭き取るときは、必ず軍手や手袋を使用して作業を行うようにしてください。
融雪剤に含まれている塩分が皮膚に付着してしまうと、炎症を起こしたり、肌トラブルにつながったりして大変危険です。
誤って皮膚に付着してしまった場合は、すぐに水で洗い流してください。
入念に下回りを洗うならガソリンスタンドに洗車を依頼する
融雪剤による錆を防ぐには、車の下回りをしっかり洗浄することが重要です。しかし、家庭用の高圧洗浄機では届きにくい箇所も多く、十分な洗浄が難しい場合があります。
そこでおすすめなのが、ガソリンスタンドなどの専門設備を備えた洗車サービスの利用です。
プロの手による下回り洗浄は、フレームや足回りの細部まで水流が届くよう設計されており、融雪剤の成分を効果的に洗い流すことができます。特に冬季や雪道を走行した後は、早めの洗車が錆の予防につながります。
車の下回りの洗車については、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。
いつまで?融雪剤が付着した車の洗車頻度
冬の高速道路など、融雪剤の影響を受けやすい道を走行した場合、走行後2〜3日以内に洗車をしておきましょう。
また降雪地帯など、一般道に融雪剤が多く散布されている道路を走行する場合は、少なくても2週間に1回程度の洗車を行ってください。
融雪剤が散布された路面を走行したあとに洗車を行う場合は、シャシまで入念に洗いましょう。
自分で洗車をする場合も、洗車機を使う場合も、車体下部を重点的に洗車することが必須です。
予防|融雪剤で車が錆びないためにはコーティングの施工を!

融雪剤で車が錆びないためには、下回り専用の防錆コーティングを施工するのが効果的です。
コーティング剤は金属表面に膜を形成し、融雪剤や水分の浸透を防ぎます。施工は専門店で行うのが一般的で、車種や使用環境に応じた塗布方法が選ばれます。
冬季に道路へ散布される融雪剤は、車の下回りに付着すると金属部分を腐食させ、錆の原因になります。
特にフレームやマフラー、サスペンションなどは直接ダメージを受けやすく、放置すると重大な故障につながるかもしれません。
新車時や冬前のタイミングでの施工が推奨されており、定期的なメンテナンスで効果を持続させることができます。
車の下回りのコーティングについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。
融雪剤について、その他の疑問・質問
こちらでは融雪剤について、その他の疑問・質問について解説していきます。
融雪剤の成分は塩化カルシウム、凍結防止剤の成分は塩化ナトリウムです。
融雪剤(塩化カルシウム)は、水と反応して熱を作り出すため、雪を溶かすのに効果的です。凍結防止剤(塩化ナトリウム)は、-20度まで凝固点を下げるため、凍結防止が期待できます。
コンクリートにヒビが発生したり、剥がれたりする可能性はあります。
融雪剤の影響で、コンクリート表面の温度が低下して体積変化が起こり、ヒビが発生します。そこに水分が浸透、凍結してクラックを拡大させ、最終的にはその部分が剥がれてくる可能性があります。
融雪剤についてのまとめ
- 融雪剤とは、雪を溶かしたり凍結防止効果があったりする塩分
- 冬の高速道路を走行したあとは、できるだけ早めに洗車をする
- 融雪剤の錆から車を守るには、コーティングの施工がおすすめ
融雪剤は、雪を融かしたり凍結防止をしたりすることで冬の道路が走りやすくなる一方、車や車の錆が心配されます。
降雪地帯を走行した後は、できるだけ早く洗車をしてください。また、事前にコーティングをしておくと、車が錆びるのを防ぎやすいです。
この記事の監修者
![]()
DUKS 受付窓口責任者
吹浦 翔太
年間84,000件のフロントガラストラブルに対応するDUKSグループで、受付窓口の責任者を務めています。
2008年から6年間、現場での実務経験を積み、現在は国内主要ディーラー各社からの修理依頼を中心に、状況の整理と修理方針の判断に携わっています。
保有資格は「JAGUフロントマスター」「ダックス事務検定2級」。
現場で培った知見をもとに、お客様にとって最善の修理をご案内します。