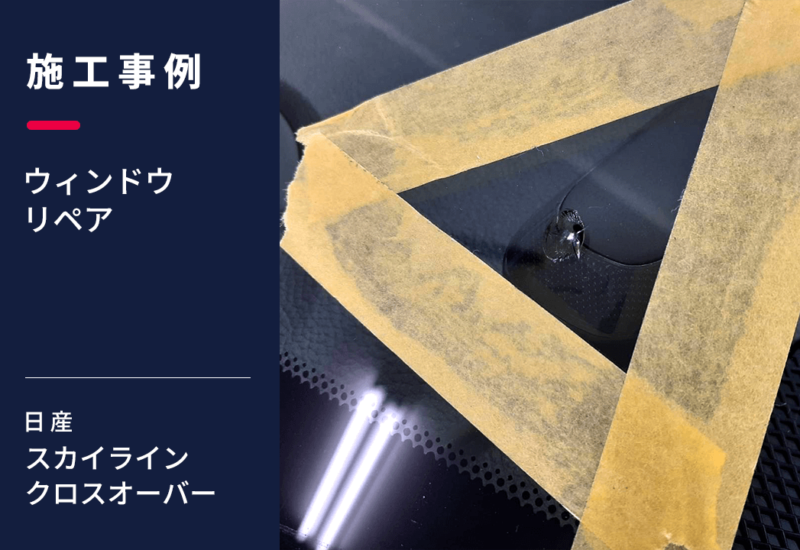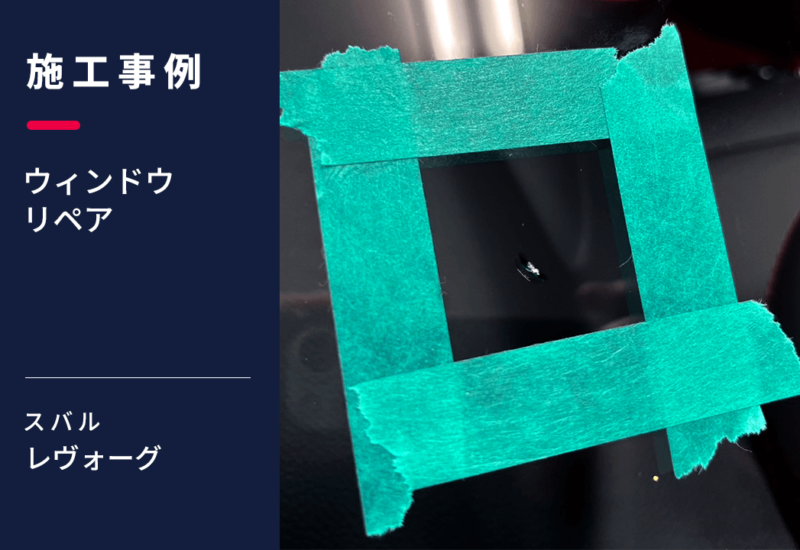犬も車酔いをする!原因や症状、犬が車酔いした際の対処法を解説

犬も人間と同様に、車酔いすることがあります。楽しいお出かけのはずが、愛犬がぐったりしてしまうと、飼い主も心配になるでしょう。
犬の車酔いには、揺れやニオイ、不安といった複数の原因が関係しており、症状も軽度から重度まで様々です。
特に小型犬や子犬、短頭犬などは車酔いしやすい傾向があるため、事前の予防や乗車中の対策が欠かせません。
今回の記事では、犬の車酔いの原因や症状を段階的に解説し、病院での相談や自宅でできる対策、便利なグッズまで丁寧に紹介します。
目次
原因|犬が車酔いをするのは何故?

犬が車酔いをする原因は、人間と共通するところがあります。犬が車酔いをする原因は、主に次の3つです。
- 車の揺れ
- 車内のニオイ
- 車への恐怖や不安
犬が車酔いをする主な原因として、車の揺れによる内耳のバランス感覚の乱れが挙げられます。
特に子犬の場合は、三半規管が未発達です。そのため、揺れに敏感で酔いやすい傾向があります。
また、車内に漂うガソリンや芳香剤のニオイが刺激となり、吐き気や不快感を引き起こすこともあります。
さらに、過去に車内で怖い思いをした経験がある犬は、乗車そのものに強い不安を感じ、精神的なストレスから体調を崩すことがあります。
こうした要因が複合的に重なることで、犬は車酔いを起こしやすくなるのです。
症状|犬が車酔いをしたときのサイン

犬が車酔いをしたときのサインについて、初期症状、軽度・中等度の症状、重度症状の3段階に分けて解説していきます。
初期症状
犬が車酔いをしたときの初期症状は、主に次の3つが挙げられます。
- 落ち着きがなくなる
- 鳴いたり吠えたり動き回ったりする
- 頻繁にあくびをする
犬が車酔いを起こした際の初期症状としてまず見られるのが、落ち着きのなさです。
普段は静かにしている犬でも、車に乗るとそわそわと座る場所を変えたり、飼い主の顔を何度も見たりして不安そうな様子を見せます。
次に、鳴いたり吠えたりする行動が目立ち始めます。これは単なる興奮ではなく、車内の環境に対する不快感や恐怖心の表れです。
また、動き回ることでその不安を紛らわせようとしている可能性があります。
そして、頻繁にあくびをするのも見逃せないサインです。これは、決して眠いわけではなく、緊張やストレスによって自律神経が乱れ、あくびという形で表れることがあります。
これらの症状は、吐き気や嘔吐といった本格的な車酔いの前兆であることが多く、早めに気づいて対処することが重要です。
軽度・中等度の症状
犬が車酔いをすると、初期の不安行動に続いて、軽度から中等度の症状が現れてきます。犬が車酔いをしたときの軽度・中等度の症状は、主に次の4つです。
- 呼吸が荒くなる
- 大量によだれが出る
- ぐったりして動かなくなる
- 体が震える
まず目立つのが呼吸の変化で、普段よりも浅く速い呼吸を「ハァハァ」と繰り返すようになります。
また、口の周りが濡れるほど大量によだれを垂らすこともあり、これは吐き気の前兆としてよく見られます。
さらに、体力を消耗してぐったりと横たわったり、動かなくなったりするケースもあります。
なかには、寒くもないのに体が小刻みに震える犬もいて、これは強いストレスや不安のサインと考えられます。
こうした症状は見逃されがちですが、犬にとってはつらい状態であるため、早めの対応が大切です。
重度症状
犬が車酔いをしたときの重度症状は、主に次の3つです。
- 嘔吐を繰り返す
- 失禁・脱糞をする
- 頭を下げてグッタリする
犬が車酔いで重度の症状を示す場合、まず繰り返し嘔吐することがあります。胃の中が空になっても吐こうとする動作が続くことがあり、体力を大きく消耗します。
また、強い不安や吐き気によって、意図せず失禁や脱糞をしてしまうこともあります。
これは、身体のコントロールが効かなくなるほどのストレス状態を意味しており、犬にとって非常に苦痛な状況です。
さらに、頭を下げてぐったりと横たわり、呼びかけにも反応が鈍くなるような様子が見られたら、車酔いが限界に達しているサインです。
こうした状態になったら、すぐに車を停めて休ませるなどして対応しましょう。
車酔いしやすい犬種はあるのか?

車酔いしやすい犬種としては、小型犬や子犬、短頭犬が挙げられます。また、過去に車酔いをしたことがある犬も車酔いをしやすいです。
たとえばチワワやパピヨン、ポメラニアンなどの小型犬は、体が軽く揺れの影響を受けやすいです。そのため、車内でのバランスを保ちにくく酔いやすい傾向があります。
子犬は三半規管が未発達で、揺れに対する適応力が低いため、車酔いを起こしやすい時期です。
また、パグやフレンチブルドッグなどの短頭犬は呼吸が浅くなりやすく、車内のストレスやニオイに敏感で体調を崩しやすいとされています。
さらに、過去に車酔いを経験した犬は、乗車そのものに不安を感じやすく、精神的な緊張が再び体調不良を引き起こすことがあります。
対策|犬が車酔いをした際の回復方法

犬が車酔いをしたら、車を停めて犬の回復を待ちます。犬が車酔いをした際の対策は、次の手順を参考にしてください。
これにより、車内のニオイや揺れから解放され、気分が落ち着きやすくなります。
ただし、無理に飲ませるのではなく、犬が自発的に飲めるように配慮してください。
その後の移動は、犬の様子を見ながら慎重に判断してください。犬の体調次第では、目的地までの運転を中止することも検討しましょう。
犬の車酔いを防ぐ方法
こちらでは、犬の車酔いを防ぐ方法として、乗車前と乗車中の対策を解説していきます。
乗車前の対策
犬の車酔いを防ぐには、乗車前の準備が重要です。
まず、動物病院で処方される犬用の酔い止め薬を事前に服用させることで、乗車中の不快感を軽減できます。
次に、満腹による吐き気を防ぐため、食事は出発の2〜3時間前までに済ませておきましょう。
また、軽く散歩をさせておくことで、緊張をほぐして排泄も済ませられるため、車内でのストレスが減ります。
そして、車内の空気がこもらないように換気をしておくと、ニオイによる不快感を和らげるのに効果的です。
これらの対策を組み合わせることで、犬の車酔いリスクを大きく下げることができます。
乗車中の対策
乗車中に犬の車酔いを防ぐには、運転の仕方や環境づくりが重要です。
まず、急ブレーキや急ハンドルを避け、できるだけ揺れを抑えた穏やかな運転を心がけましょう。揺れが少ないほど、犬の三半規管への負担が軽減され、酔いにくくなります。
また、車内の空気がこもるとニオイによる不快感が増すため、窓を少し開けてこまめに換気を行うことも効果的です。
ただし、窓から愛犬が顔を出したり飛び出したりしないよう、窓の開けすぎには気を付けてください。
さらに1〜2時間に1回は車を停めて、10〜15分ほどの休憩をとりましょう。
長時間の乗車は犬にとって大きなストレスとなるため、外の空気を吸わせたり軽く歩かせたりすることで、体調の安定につながります。
帰宅後|犬のアフターケア
犬を車に乗せて帰宅した後は、アフターケアにも配慮してください。
まず、静かな環境で1〜2時間ほど安静にさせることが大切です。すぐに食事を与えると胃に負担がかかるため、体調が落ち着いてからにしましょう。
食事の内容は、脂肪分の多いものや刺激の強いものを避け、消化の良いフードに切り替えると回復を助けます。
また、一度に多く食べさせるのではなく、少量ずつ複数回に分けて与えることで、胃腸への負担を軽減できます。
こうした配慮が、次回の乗車時の車酔い予防にもつながります。
犬が乗車する際に、あったら便利なグッズ

犬が車に乗る際にあると便利なグッズは、次の物が挙げられます。
- リード、首輪
- クレート、キャリー
- トイレシーツ
- タオル
- 掃除グッズ
- 水
- 携帯皿
- おもちゃ
まず、リードと首輪は乗降時のコントロールに欠かせず、万が一の飛び出し防止にも役立ちます。
車内ではクレートやキャリーを使うことで揺れによる不安を軽減でき、犬自身も安心して過ごせます。
万が一の粗相に備えてトイレシーツを敷いておくと掃除が楽になり、タオルは嘔吐時の処理や体を拭く際に重宝します。
掃除用のウェットティッシュや、ビニール袋も常備しておくと安心です。水分補給用のボトルや、携帯皿も忘れずに用意してください。
犬が退屈しないようお気に入りのおもちゃを持参すると、乗車中のストレス緩和につながります。
犬の車酔いについてのまとめ
- 犬が車酔いをするのは、車のニオイや車内の揺れ、車への不安が原因
- 車酔いしやすい犬種は、主に小型犬・子犬・短頭犬
- 犬が車酔いをしたら安全な場所に車を停めて、犬を車外に出して新鮮な空気を吸わせる
犬も人間と同様に、車酔いすることがあります。特に車酔いしやすい犬種は、事前の予防や乗車中の対策、病院での相談が重要です。
今回紹介した原因や症状、対策を参考にして、愛犬との快適なドライブを楽しんでください。
この記事の監修者
![]()
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。