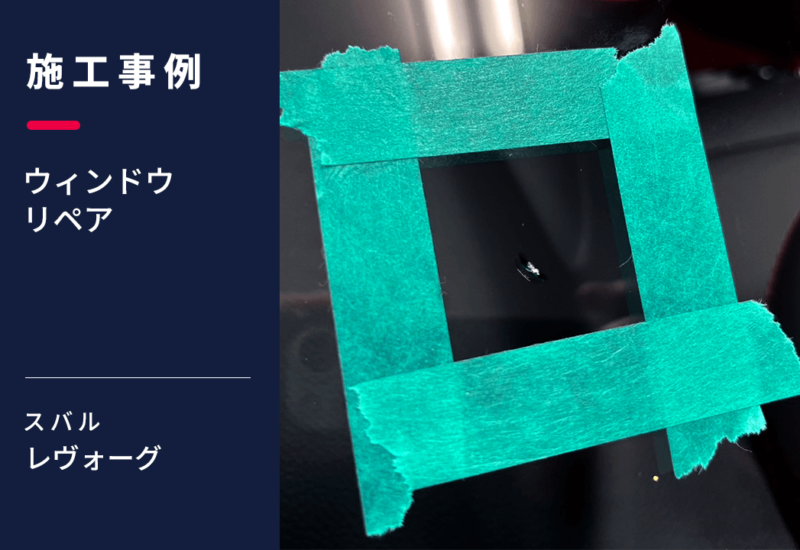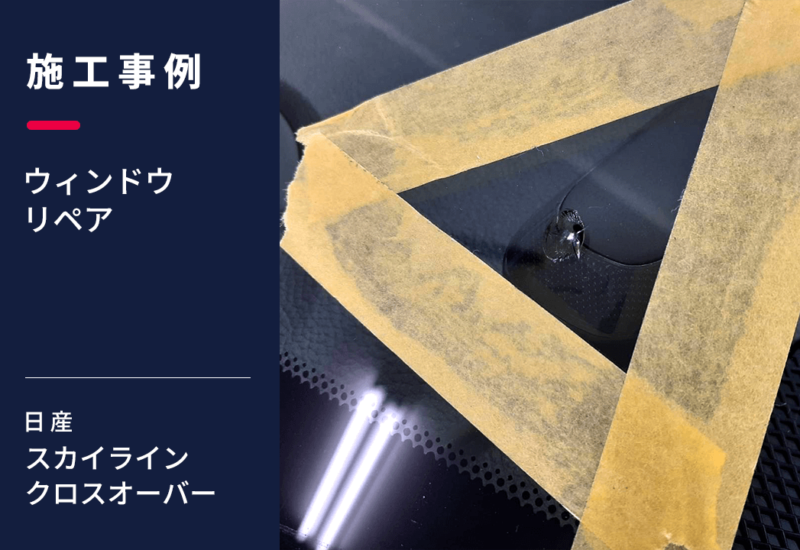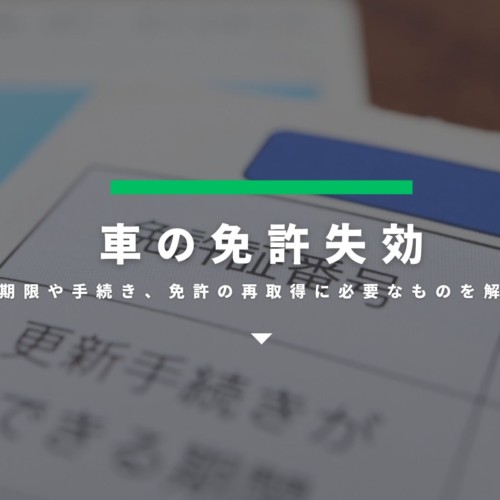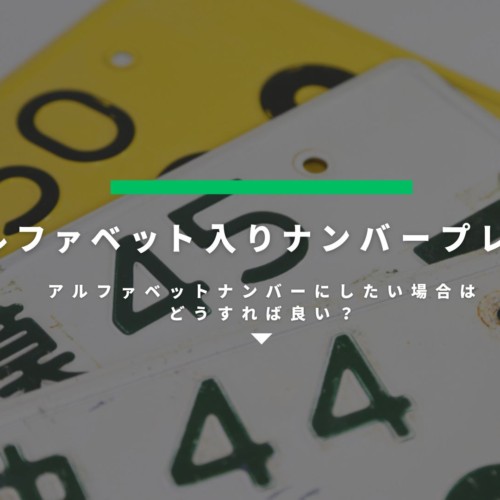はみ出しタイヤとは?車検のポイント、原因や対策について解説

はみ出しタイヤとは、車のタイヤがフェンダーの外側にはみ出している状態を指します。
見た目のカスタム性を高めるためにホイールを交換したり、インチアップやスペーサーを装着した結果、意図せずタイヤが基準を超えてはみ出してしまうケースが少なくありません。
しかし、タイヤのはみ出しは車検に影響する重要なポイントであり、基準を満たさないと不適合となる可能性があります。
今回の記事では、はみ出しタイヤの定義や原因、車検に通すための対策について解説していきます。
目次
はみ出しタイヤとは?

「はみ出しタイヤ」とは、車両の側面にあるフェンダー(泥除け)からタイヤの一部が外側にはみ出している状態を指します。
フェンダーは、走行中にタイヤが巻き上げる泥や小石を車外に飛ばさないための部品です。
そのフェンダーから、タイヤがこれを超えて露出すると、他車や歩行者への飛散リスクが高くなります。
ホイール交換やオフセット調整によってタイヤの位置が外側にずれると、見た目のカスタム性は向上する一方で、保安基準に抵触する可能性があります。
車検では、タイヤがフェンダーからはみ出していると不適合と判断されることがあり、見た目だけでなく安全性や法令遵守の観点からも注意が必要です。
はみ出しタイヤは車検に通るのか?
はみ出しタイヤが車検に通るかどうかには、基準があります。具体的に「10mm未満」のはみ出しなら、車検に通るとされています。
こちらでは、はみ出しタイヤや、タイヤ以外のはみ出しは大丈夫なのかについて解説していきます。
はみ出しタイヤは「10mm未満」なら車検に通る
乗用自動車(乗車定員9人以下)の場合、タイヤのはみ出しは「10mm未満」であれば許容範囲とされています。
ちなみに、貨物車や乗車定員10名以上の乗用車の場合、1mmでもタイヤがはみ出していると車検に通りません。
※注意※タイヤ以外のはみ出しは認められない
はみ出しがOKなのは、あくまでもタイヤだけです。つまり、タイヤを大きくしてもホイールを大きくしても良い、というわけではありません。
厳密にはみ出してOKなのは、タイヤの側面に記された銘柄・サイズ・ブロックなどを指す「ラベリング」です。
また、「リムガード」と呼ばれる、ホイールリムを縁石などから保護するためのタイヤ突起部分も対象になります。
【リムガードのタイヤ画像】

はみ出しNGなのは、ホイールや取り付けナットなどです。これらに関しては、フェンダー内に収める必要があります。
- はみ出しOK:ラベリング、リムガード
- はみ出しNG:ホイール、ホイールステップ、ホイールキャップ、ホイールナット
車検におけるタイヤ部分のポイント
車検を通すためには、ホイールや取り付けナットなどが、フェンダーよりはみ出していないことです。車検には以下の項目が存在します。
- サイドスリップ検査:ハンドルを真っ直ぐの状態にして、車が直進できるかの検査
- 各種メーター検査:スピードメーターと実際の速度に、大きな誤差がないかの検査
- ブレーキ検査:ブレーキペダル・サイドブレーキの効き具合の検査
はみ出しタイヤの場合だと、車体とタイヤの規格が合わないので、これらの検査が通らない可能性があります。
車検については、以下の項目でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。
はみ出しタイヤの測定方法

タイヤが外側にはみ出しているかどうかの測定方法は、次の画像と手順を参考にしてください。
はみ出しタイヤは警察に捕まる?

はみ出しタイヤは「不正改造」という扱いになり、罰金や反則金の対象になる可能性があります。
不正改造扱いになると、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の懲罰」に加えて、「15日以内の整備命令」が下されます。
ただし悪質性が低いと見なされれば、整備不良として「違反点数1点+反則金7,000円」、もしくは「違反点数2点+反則金9,000円」で済む場合もあります。
とはいえ取り締まる警察官の判断にもよるので、不正改造扱いにならないよう、はみ出しタイヤには気を付けましょう。
はみ出しタイヤの危険性
はみ出しタイヤによるトラブルは、次のケースが考えられます。
- 巻き込み、接触事故
- 小石や泥などが飛び散る
- タイヤバースト
- スピン事故
- 実際の速度表示と誤差が出る
巻き込み、接触事故
交差点でのカーブや、狭い道で歩行者などとすれ違うときに、巻き込みや接触事故を起こすリスクが高くなります。
小石や泥などが飛び散る
運転中に小石や泥、水たまりの水などを飛び散らさないように存在するのが「フェンダー」です。しかし、フェンダーからタイヤがはみ出すと、これらのものが飛び散りやすくなります。
タイヤバースト
タイヤがはみ出すことで、フェンダーの切れ角と当たり、タイヤの破損(バースト)が起こりやすくなります。
スピン事故
フェンダーと接触すると、タイヤロックがかかる可能性があります。運転中にタイヤロックがかかると、車がスピンして大事故を起こすリスクが存在します。
実際の速度表示と誤差が出る
タイヤの大きさが変わると、スピードメーターと実際の速度に大きな誤差が出る可能性があります。しかし、よほど大きなタイヤに変えない限り、大きな誤差は出ません。とはいえ、速度規制を守っているつもりでも、実際にスピード違反をして取り締まられる可能性はあります。
原因|はみ出しタイヤは何故起こる?
そもそも、何故はみ出しタイヤになるのでしょうか?はみ出しタイヤになってしまうケースは、主に次の3パターンです。
- ホイール交換の際にインセットが純正と異なる
- インチアップをした場合
- ホイールスペーサーの装着
ホイール交換の際にインセットが純正と異なる
ホイールを交換する際に、純正と異なるインセットのホイールを選ぶと、タイヤの位置が外側にずれてフェンダーからはみ出すことがあります。
インセットとは、ホイールの中心から取り付け面までの距離を示すものです。純正の数値より小さくなるほど、タイヤがはみ出す恐れがあります。
インチアップをした場合
インチアップとは、ホイールの直径を大きくすることで、デザイン性や走行特性の変更を図るカスタムの手法です。
インチアップの際にサイズ選びを誤ると、リム幅が広くなる影響で、タイヤが車体からはみ出してしまうケースがあります。
インチアップをするときは、タイヤの厚みとリム幅の選択に注意してください。
ホイールスペーサーの装着
ホイールスペーサーとは、ホイールとハブの間に設置するパーツのことです。
厚みがあると、ホイールの位置が外側に移動してしまいます。そのため、ホイールスペーサーに厚みがあればあるほど、タイヤがはみ出す可能性が高いです。
見た目の迫力を出したり、ブレーキとの干渉を避ける目的で使われますが、スペーサーの厚みは適切に選ばないといけません。
フェンダーと回転物の最外部に、どれくらいの余裕があるかを測定しましょう。
対策|足回りのカスタムやドレスアップはプロに相談する
はみ出しタイヤにならないための対策として、足回りのカスタムやドレスアップはプロに相談するのが懸命です。
たとえばタイヤ専門店の場合、ホイール交換やホイールスペーサーの装着など、パーツの最適な選び方を熟知しています。
また、タイヤやホイールを変える際、はみ出し以外にも、ロードインデックスの問題やスピードメーターの誤差が起こらないように注意をしないといけません。
タイヤのはみ出しによっては、車検の合否や安全性にも関わるため、タイヤ専門店のプロに相談するのがおすすめです。
はみ出しタイヤについてのまとめ
- はみ出しタイヤとは、見た目のカスタムやパーツ交換によってタイヤがフェンダーからはみ出す状態
- タイヤのはみ出しは「10mm未満」なら車検に通る
- 10mm以上になると、罰金や反則金の対象になる可能性がある
はみ出しタイヤは、車検の際に厳密な基準があり、不適合と判断されると不合格となります。
安全性や法令遵守のためにも、足回りをカスタマイズする際は、タイヤ専門店のプロに相談しましょう。
この記事の監修者
![]()
DUKS 受付窓口責任者
吹浦 翔太
年間84,000件のフロントガラストラブルに対応するDUKSグループで、受付窓口の責任者を務めています。
2008年から6年間、現場での実務経験を積み、現在は国内主要ディーラー各社からの修理依頼を中心に、状況の整理と修理方針の判断に携わっています。
保有資格は「JAGUフロントマスター」「ダックス事務検定2級」。
現場で培った知見をもとに、お客様にとって最善の修理をご案内します。