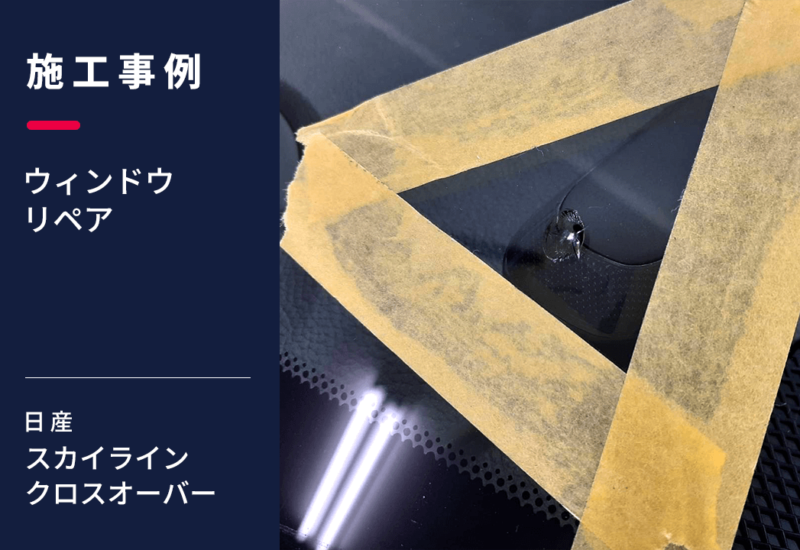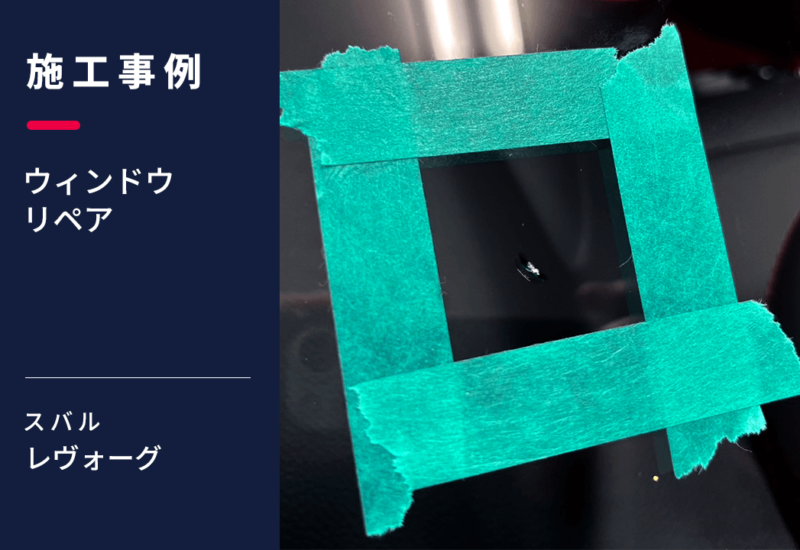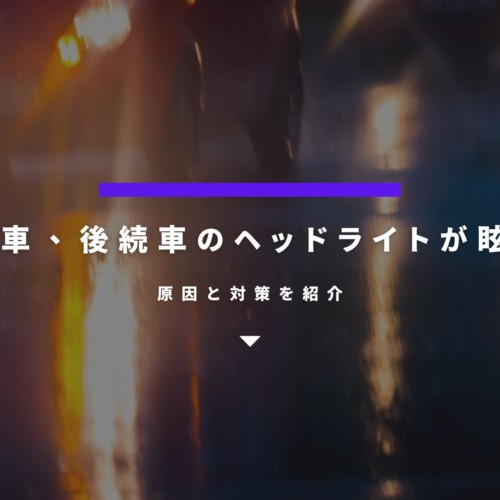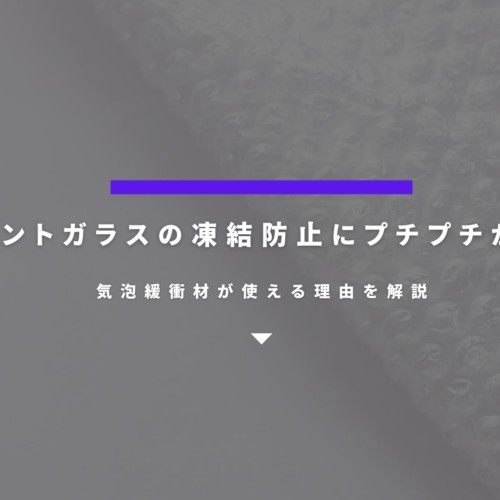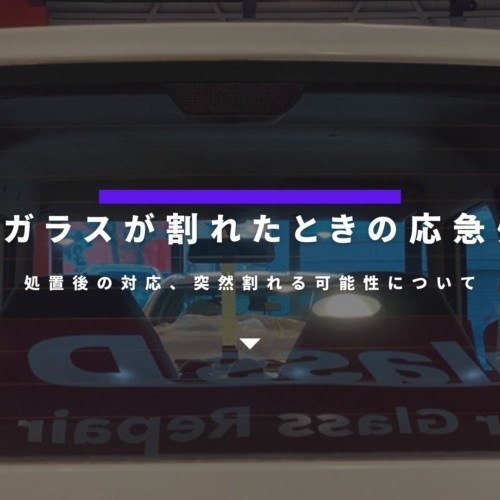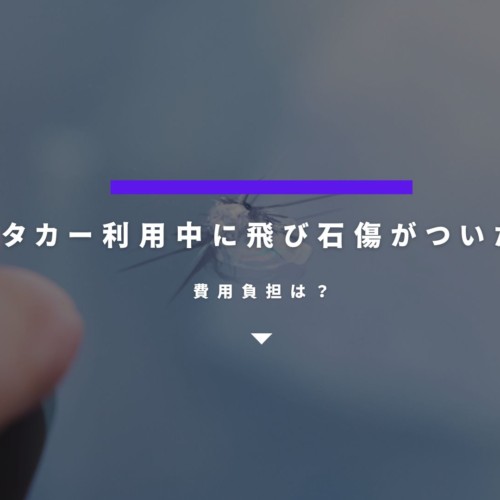応急救護処置とは?応急救護の手順や自動車学校の応急救護講習について
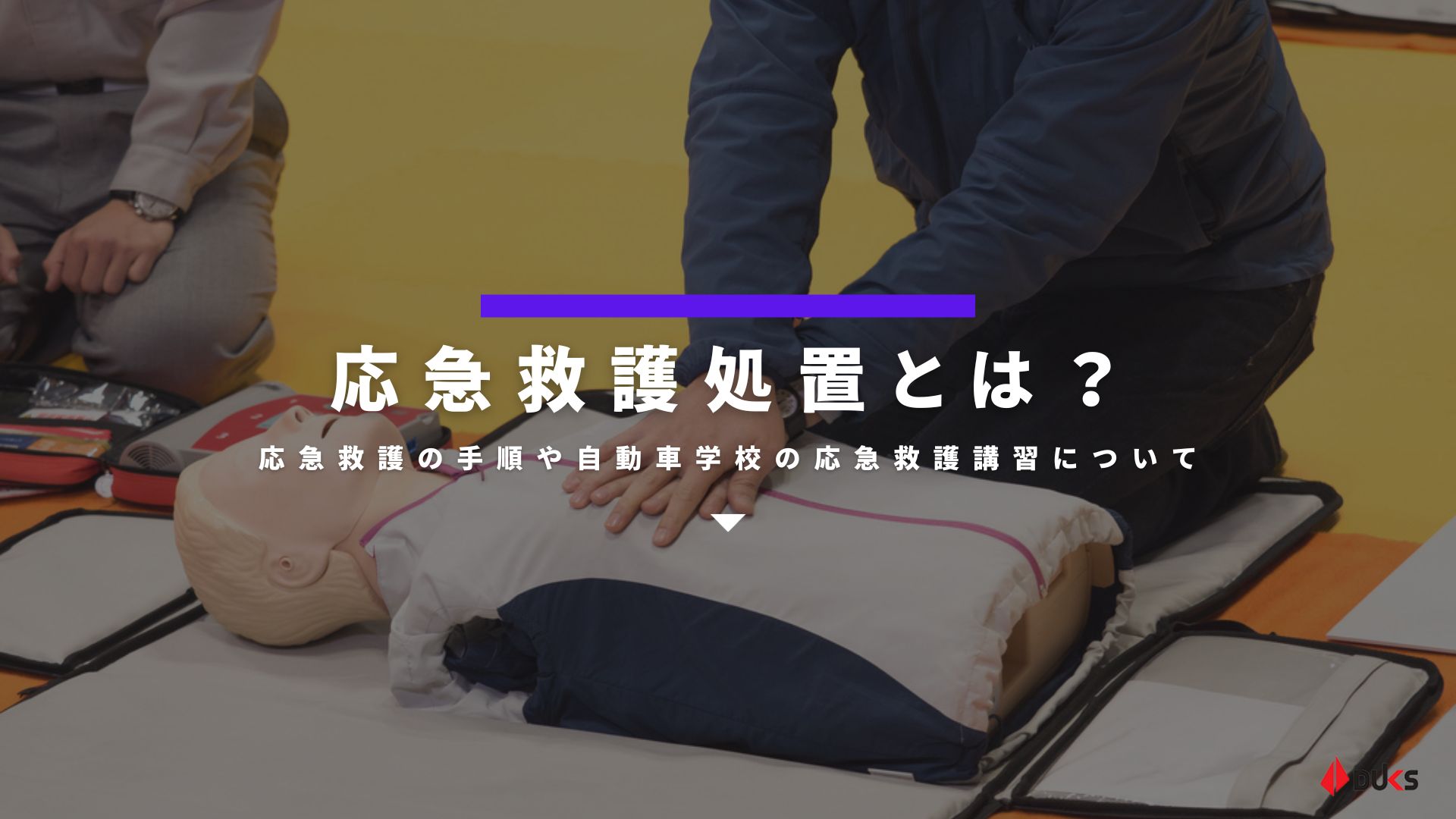
「自分の身には起こらない」と思っていても、交通事故の現場に遭遇しないとは限りません。内閣府の発表によると、交通事故は毎年30〜40万件ほど発生しています。
交通事故は負傷者が出る可能性が高く、ドライバーや歩行者が命の危機に瀕するケースも少なくありません。応急救護処置の適切な方法を把握していれば、負傷者を救命できる可能性がアップします。
そこでこの記事では、応急救護処置の必要性から手順、自動車教習所の応急処置講習について解説していきます。
目次
応急救護処置とは?迅速な応急救護処置の必要性
交通事故の現場における、負傷者を救命する処置としては、以下の2つが存在します。
- 一次救命処置(BLS):BLSは「Basic Life Support」の略で、心臓マッサージ、人工呼吸、AEDおよび気道異物除去を行います
- ファーストエイド:止血、骨折の手当などを行います
通報から救急車が現場に到着するまでに、平均で約8分かかります。負傷者の命が助かる可能性は、負傷から時間が経過すればするほど低下していきます。
消防庁の発表によれば、心肺停止状態では「3分以内の処置」、呼吸停止状態では「10分以内の処置」を行うことで、救命率を50%まで上げることができます。
つまり救急車が到着するまでのあいだ、現場の救護処置が救命に重要な役割を担うのです。
応急救護処置は道路交通法で義務付けられている
車の運転中に交通事故に巻き込まれた際に、自分が無事で負傷者がいる場合は、応急救護処置をしなければいけません。応急救護処置については、道路交通法で義務付けられています。
道路交通法第72条
引用:第七十二条(交通事故の場合の措置)
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
また応急救護処置以外にも、警察への通報をする必要があります。
応急救護処置する際は、安全な場所の確保を
二次災害の危険がある場合を除き、原則として負傷者を移動するのは危険です。発炎筒を焚くか、停止表示板を用いて安全の確保を行いましょう。路肩や道路外の広場など、車の通行が少ない場所での処置がベストです。
・交差点
・カーブ
・坂道
・交通量の多い大通り
これらの場所では、安全確保について慎重に行ってください。
応急救護処置の手順と、具体的な処置方法
交通事故で負傷者が出た場合は、119番で救急車を呼びAEDが周囲にないか探しましょう。AEDが到着するまでの間は負傷者の反応を見て、場合によっては自分が心肺蘇生を行う必要があります。
応急救護処置の手順
心肺蘇生からAEDの使用までは、以下の手順で応急救護処置を行ってください。
AEDはコンビニやスーパー、ドラッグストアなどの商業施設にも備えてあります。周りに人がいる場合は、協力しながら行ってください。
負傷者の反応を見る
まずは、負傷者の意識を確認する必要があります。肩を軽くたたきながら、「大丈夫ですか?」などと耳元で声をかけましょう。何らかの返事があれば、訴えを聞いて手当を行ってください。
意識はあるけれども返事ができない場合は、負傷者を平らな地面に寝かせ、回復体位にします。回復体位とは気道を確保する体位のことで、以下がその手順です。
呼吸の観察をして心臓マッサージを行う
胸部と腹部の動きを見て、「呼吸がない」あるいは「普段どおりの呼吸かどうかの判断がつかない」場合は、胸骨圧迫(心臓マッサージ)を開始します。
※乳児(1歳未満)である場合、2本指でマッサージしてください。
※8歳未満の小児である場合、胸の厚み1/3が沈み込むくらいにマッサージしてください。
人工呼吸
30回連続で胸部を圧迫したら、人工呼吸を行います。
息を吹き込んだら、負傷者の呼吸を観察しましょう。変化がなければ、再び心臓マッサージ30回→人工呼吸2回します。
AEDが到着するまでは、この作業を絶え間なく繰り返してください。
AEDを使用する
基本的には機械が音声で操作手順を案内しますが、念のためAEDの使用手順を確認しておきます。
音声画面に加えて、液晶画面で案内してくれます。案内に従って落ち着いて対処しましょう。小さいお子様の場合は、「小児モード」に切り替えてください。
ちなみに、AEDは自動で電気ショックが必要かどうかを判断して、必要ない場合は「ショックは不要です」という音声が流れます。その際は、直ちに胸骨圧迫から人口呼吸の流れで心肺蘇生を再開してください。
止血方法(出血がある場合)
負傷者から出血がある場合、「直接圧迫止血」もしくは「間接圧迫止血」で止血する必要があります。ただし、「間接圧迫止血」は知識がないと難しい方法なので「直接圧迫止血」をオススメします。
やり方は、ハンカチやタオルを傷口に直接当てて出血を抑えます。患部を高い位置に持ち上げて止血すると、より効果的です。止血を行う際は、感染症を防ぐために血液に直接触れてしまわないよう、ビニール袋などを手に被せて止血を行いましょう。
自動車教習所の応急救護講習について
応急救護処置については、自動車教習所のカリキュラムに組み込まれており、卒業試験前に効果測定が行われます。
「自動車学校で、応急救護講習を受けるのは恥ずかしい。」と思う人もいますが、講習を受けないと免許の取得はできません。
教習所の応急救護講習はどんな感じなのか?
自動車教習所の応急救護講習ですが、基本的には以下の流れで行います。
まずは映像や教官の説明で、事故で負傷者が出た場合の措置、人工呼吸や心臓マッサージの方法について学びます。
説明を受けたあとは人形を使い、教官がお手本を見せます。内容は「応急救護処置の手順と、具体的な処置方法」の項目で、解説したものと同様です。
生徒による実践では、人形を使った心臓マッサージと人工呼吸を行います。「人工呼吸用携帯マスク」を使うため、実際には口に触れることはありません。
講習を免除できる人について
自動車教習所では応急救護講習を受ける必要がありますが、以下のようなケースや資格保持者の場合は講習を免除されます。
- 普通免許、準中型免許、大型二輪免許、普通二輪免許のいずれかを取得している
- 上記の免許証のいずれかを更新できず失効した人。もしくは事情により、やむなく失効して免許試験の一部免除を受けることができる人
- 歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、救急救命士など応急救護措置の知識を得ていると証明できる人
持ち物や服装
自動車教習所で応急救護講習を受ける際は、持ち物を指定されることがあるので把握しておきましょう。また、服装もできるだけ動きやすい格好が良いです。
たとえばシャツにジーンズなど、カジュアルで動きやすい格好で臨むのがおすすめです。女性の場合はスカートを避けて、髪の毛を束ねられるようにヘアゴムを持参してください。
また靴も脱ぎ履きすることがあるので、スニーカーで講習を受けましょう。ブーツやチャック付きの靴は脱ぎ履きも大変で、講習の進行の妨げにもなります。
応急救護の教習に行く時の持ち物は、その自動車学校によっても変わってくるのでそれぞれ指示されたものを持っていくようにしましょう。
応急救護処置をしっかりと学びたい人へ
しっかりと応急救護処置について学びたい人は、以下の場所で講習を受けることができます。
- 各消防本部や消防署の「救命講習会」
- e-ラーニングの「応急手当WEB講習」
一般の人に向けた救命講習については、お住まいの消防本部・消防署で「救命講習会」を実施しています。
また救命講習会に行く時間がない人の場合は、e-ラーニングの「一般市民向け 応急手当WEB講習」を受けることが可能です。
応急救護処置について自動車教習所で学びますが、内容をずっと覚えている人は多くないでしょう。またAEDを使用できるようになったのは、2004年の7月からなので、それ以前に免許を取得した人は、AEDに触れたことのない人もいると思います。
そのため応急救護処置について改めて学びなおしたい人は、救命講習会や応急手当WEB講習をぜひ参考にしてください。
参考:政府広報オンライン|いざというときのために応急手当の知識と技術を身につけておきましょう
応急救護処置についてのまとめ
- 迅速な応急救護処置を行うことで、救命率は上げられる
- 事故現場で負傷者がいたら、まずは意識の確認をして適切な処置を行う
- 自動車教習所で応急救護講習のカリキュラムを受けないと、免許を取得できない
応急救護処置は、救急車が到着するまでの命綱です。応急救護処置次第で人命を大きく左右し救命率も変わるので、積極的に人命救護にあたってください。
周囲に人がいる場合は協力を呼びかけ、専門家や詳しい人がいた場合は、指示に従って適切に動くようにしましょう。
この記事の監修者
![]()
DUKS 受付窓口責任者
吹浦 翔太
年間84,000件のフロントガラストラブルに対応するDUKSグループで、受付窓口の責任者を務めています。
2008年から6年間、現場での実務経験を積み、現在は国内主要ディーラー各社からの修理依頼を中心に、状況の整理と修理方針の判断に携わっています。
保有資格は「JAGUフロントマスター」「ダックス事務検定2級」。
現場で培った知見をもとに、お客様にとって最善の修理をご案内します。