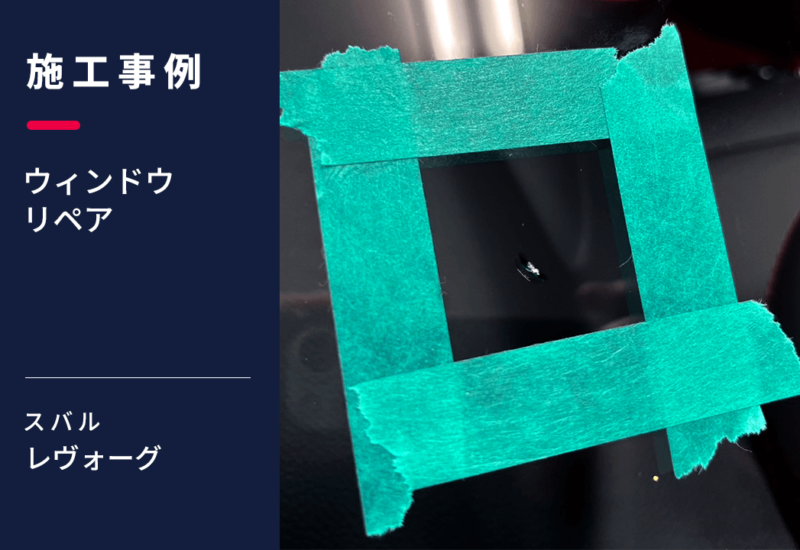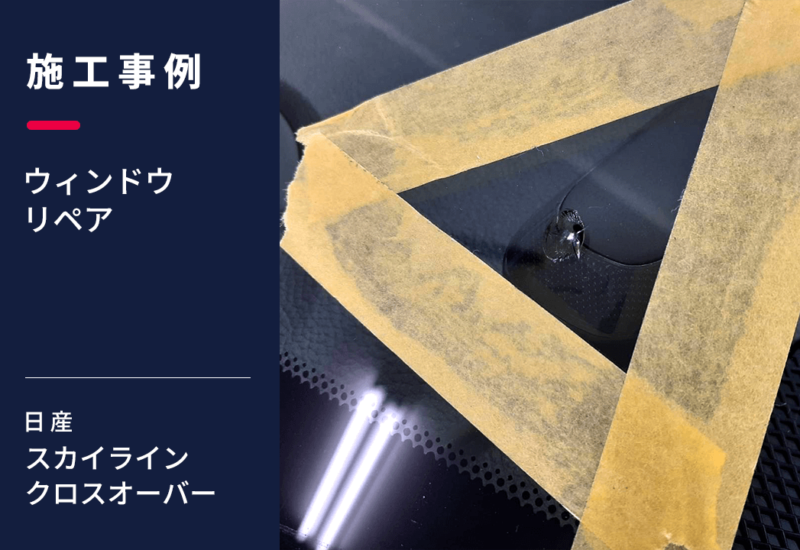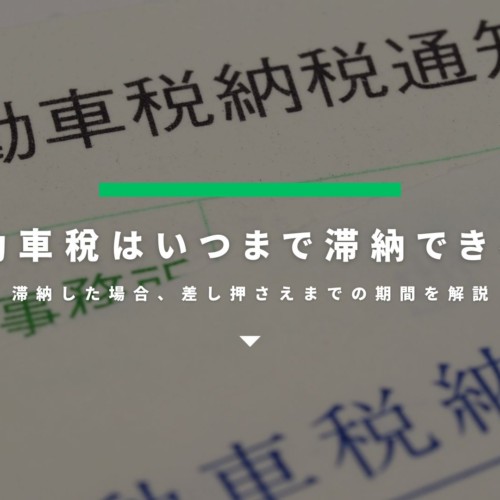追い越し禁止場所とは?「追い越し」と「追い抜き」の違いについても解説

追い越しの禁止場所をご存知でしょうか?道路交通法では、交通の安全を守るために「追い越し」が禁止されている場所がいくつか定められています。
追い越しとは、進路を変更して前方の車両の側方を通過し、前に出る行為を指します。混同されがちな「追い抜き」とは異なる種類の運転動作です。
こうした違いを理解しないまま運転すると、思わぬ事故につながることもあります。
今回の記事では、追い越しが禁止されている具体的な場所やその理由等について解説していきます。
目次
追い越しとは?「追い越し」と「追い抜き」の違い
こちらでは追い越しとは何かについて、追い抜きとの違いも交えて、具体的な行動内容を解説していきます。
追い越しとは?
追い越しとは、進行中の車両の前方に出るために、進路を変更して追い抜く行為を指します。
道路交通法第2条の21では、追い越しの定義について次のように記載しています。
道路交通法第2条の21(定義)
追越し:車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
出典:道路交通法 | e-Gov 法令検索
具体的には、次の手順が追い越しの行動に当たります。
追い抜きとは?
追い抜きとは、前の車が停止または極端に低速で走行している際に、進路変更を伴わずにそのまま前方に出る行為です。つまり、追い越しとは進路変更の有無に違いがあります。
追い抜きについては、道路交通法の規定はありません。進路変更を伴う「追い越し」と区別するために「追い抜き」と呼ばれています。
追い越し禁止場所
追い越し禁止場所は、具体的に次の6つです。
- 追い越し禁止線(オレンジ色の実線)
- 車線変更禁止の標識・標示がある場所
- 道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近または勾配の急な下り坂
- 交差点およびその手前30m以内
- 横断歩道や自転車横断帯の手前30m以内
- 車両通行帯のないトンネル
追い越し禁止線(オレンジ色の実線)

道路にはオレンジ色や白色の線が引かれていますが、追い越しについては次の意味があります。
- オレンジ色:対向車線にはみ出しての追い越しは禁止
- 白色の実線:線を越えての追い越し禁止
- 白色の破線:追い越しが可能
オレンジ色の実線は、センターライン(中央線)として引かれている場合が多く、対向車線にはみ出しての追い越しは禁止されています。
白色の実線は、道路幅が片側6m以上の道路に設けられているため、線をはみ出しての追い越しが禁止されています。線を越えないのであれば、前方車両を追い越してもかまいません。
白色の破線は、車線変更や追い越しが可能な区間です。
追い越し禁止線については、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。
車線変更禁止の標識・標示がある場所

※画像左:下部に補助標識があり、追い越し禁止。車線内の追い越しも不可能
※画像右:車線の右側部分にはみ出さなければ、追い越し可能
車線変更禁止の標識や標示がある場所では、当然ながら追い越しも禁止されます。
これは、車線変更を伴う追い越しが安全に行えないと判断された区間に設けられています。たとえば、交差点付近やトンネル内、合流地点などです。
こうした場所では、進路変更によって他車との接触や事故の危険が高まるため、追い越し行為そのものが法律で制限されています。
標識や標示がある場合は、たとえ前方の車が遅くても無理に追い越そうとせず、指示に従って走行することが求められます。
道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近または勾配のある急な下り坂

道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近または勾配のある急な下り坂は、道路交通法・第30条により追い越しが禁止されています。
これらの場所では前方の状況が見えにくく、対向車の存在を確認しづらいです。追い越しをすると、正面衝突などの重大事故につながる危険性があります。
特に上り坂の頂上では、登り切った先の交通状況が不明なまま追い越すことになり、非常に危険です。
また、急な下り坂では車両の制動距離が伸びやすく、追い越し中にスピードが出すぎて制御不能になるリスクがあります。
交差点およびその手前30m以内

交差点内で追い越しのための車線変更は、道路交通法・第30条により禁止されています。
これは、交差点付近では車両の進路変更や右左折、歩行者の横断などが重なり、事故のリスクが高まるためです。
特に、信号のない交差点や見通しの悪い場所では、対向車や歩行者の動きが予測しづらく、追い越しによって重大な事故につながる恐れがあります。
また、交差点の手前30メートルという距離は、運転者が安全に減速・停止できるように配慮された範囲であり、標識がなくてもこのルールは適用されます。
横断歩道や踏切およびその手前30m以内

横断歩道や踏切およびその手前30m以内も、道路交通法・第30条により追い越しが禁止されています。
横断歩道では、歩行者が渡ろうとしているかどうかを確認する義務があります。追い越しによって前方の視界が遮られると、歩行者の存在に気付くのが遅れるため危険です。
踏切においても、前の車両が一時停止している場合に追い越すと、踏切内で立ち往生するリスクが高まり、重大事故につながる恐れがあります。
標識がなくてもこの30メートルの規定は適用されるため、運転者は常に周囲の状況に注意し、安全を最優先に行動する必要があります。
車両通行帯のないトンネル

車両通行帯のないトンネルでの追い越しも、道路交通法・第30条によって禁止されています。
トンネル内は暗く、道幅が狭く対向車との距離が近いため、追い越しによる事故のリスクが高いです。
特に片側一車線のトンネルでは、追い越しの際に対向車と正面衝突する危険があり、わずかな判断ミスが重大な事故につながりかねません。
また、トンネル内では音の反響や照明の影響で周囲の状況を把握しづらく、緊急時の回避行動も困難です。
そのため、たとえ前の車が遅く感じられても、トンネル内では追い越しをせず、安全な場所に出るまで我慢することが求められます。
トンネル内での追い越しについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。
追い越しを自重した方が良いケースとは?
追い越し禁止場所でないとしても、次の場所では追い越しをすると危険です。
- 二重追い越し
(前方車両が自動車や原付、軽車両などを追い越そうとしている場面) - 前方車両が右折のために進路を変えようとしている
- 対向車線からの、車両や路面電車の進行を妨げるようとする追い越し
- 後方の車両が自分の車を追い越そうとしているとき
これらのシーンでは、たとえ追い越しが大丈夫な場所だとしても、無理な追い越しになるため、事故につながるリスクが高くなります。
追い越しの違反による違反点数と反則金
追い越し禁止場所で追い越しをした場合、違反点数は2点が加算され、普通車の場合は反則金9,000円が科されます。
違反点数:2点
普通車の反則金:9,000円
大型車の反則金:12,000円
二輪車の反則金:7,000円
小型特殊車・原付の反則金:6,000円
追い越し目的での車線変更禁止についてのまとめ
- 追い越しとは、進行中の車両の前方に出るために、進路を変更して追い抜く行為
- 追い越し禁止場所は、オレンジ色の実線や車線変更禁止の標識・標示がある場所、道路交通法で禁止されている場所
- 追い越し違反をすると違反点数は2点、反則金9,000円(普通車)
追い越しには「追い抜き」との違いがあり、場所によっては法律で禁止されています。交通ルールを正しく理解しないまま運転すると、事故の原因になることもあります。
今回紹介した禁止場所や種類を知っておくことで、安全運転につながります。追い越しの判断は慎重に行いましょう。
この記事の監修者
![]()
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。