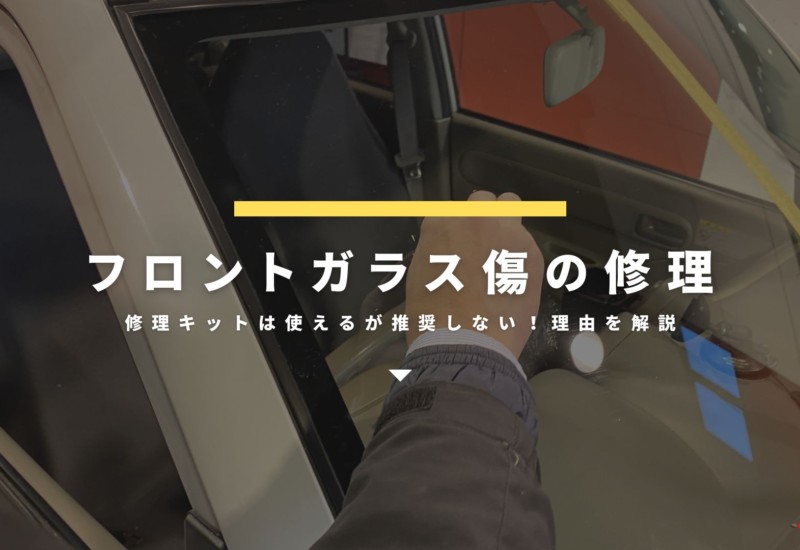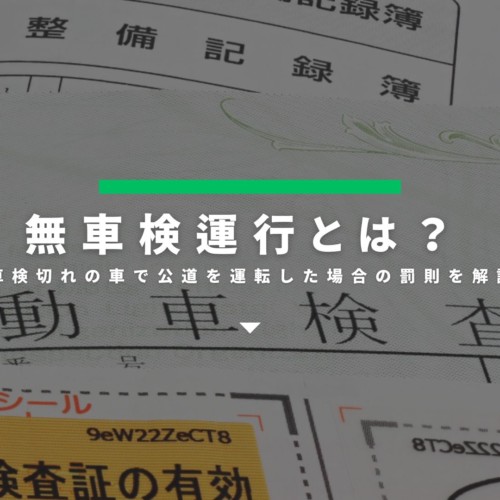導流帯(ゼブラゾーン)の設置基準やルールについて|右折時に起きる事故や過失割合も解説
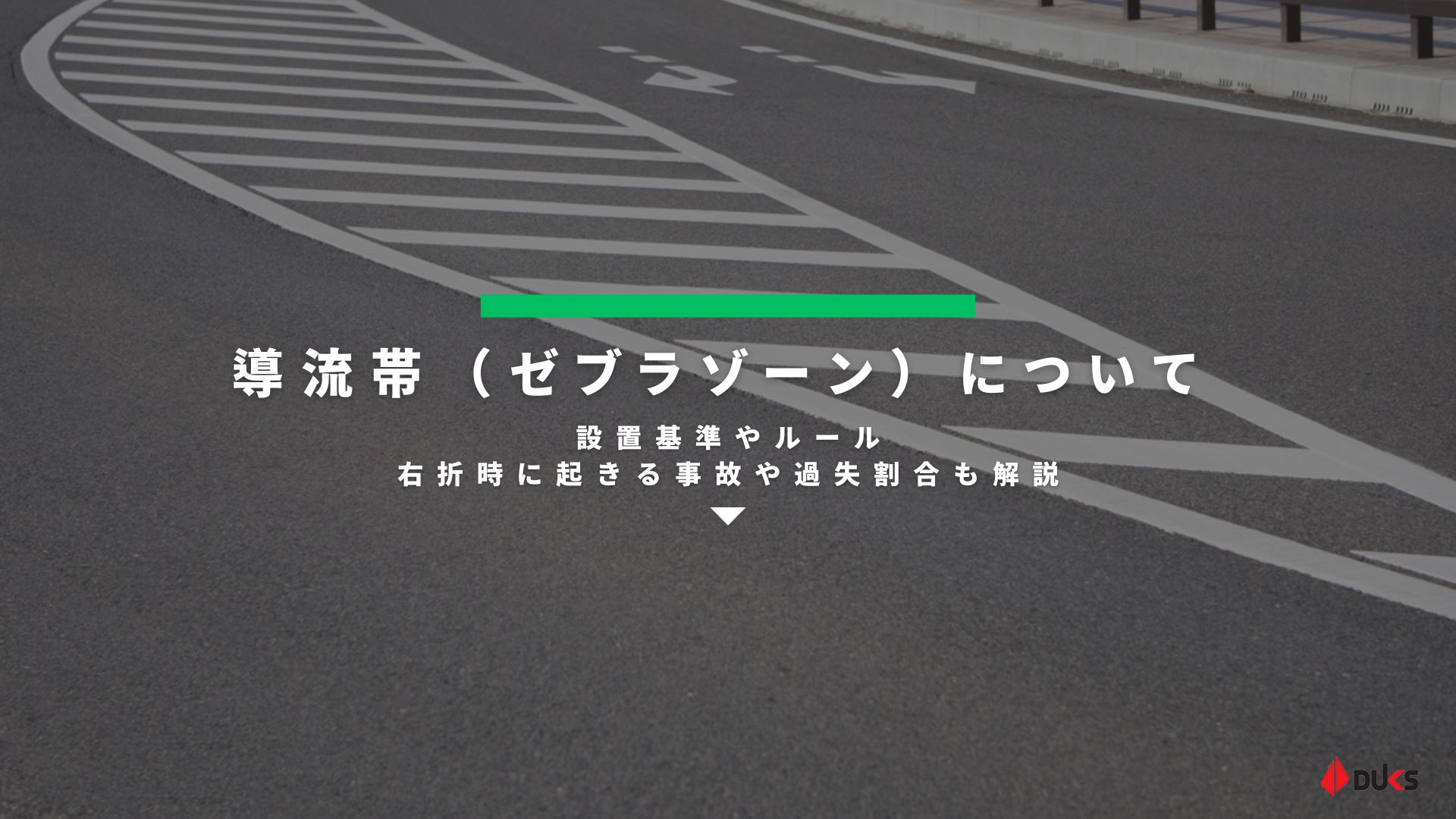
導流帯とは道路標示の一つで、斜めの白線を白い枠線で囲んでいる区画線のことです。車の安全運転、円滑に走行できることを目的として設置されています。
その見た目が、シマウマを彷彿とさせることから「ゼブラゾーン」とも呼ばれています。
よく見かける導流帯ですが、実際に何のために存在するのか、分からない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、導流帯の設置基準や導流帯で起こりやすい事故、導流帯に似た道路標示について解説していきます。
目次
導流帯(ゼブラゾーン)の設置基準や設置場所を、道路交通法から解説
こちらでは導流帯(ゼブラゾーン)の設置基準や目的、設置場所について解説していきます。
導流帯の設置基準や目的
導流帯の設置基準は「車両の安全、かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所」です。
これは道路交通法の「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」により、基準が設けられています。
導流帯を設置する目的は、以下の通りです。
- 広い交差点のある道路で、交通渋滞や事故を防止するため
- 交差点の道路形状が複雑である場所で、交通渋滞や事故を防止するため
- 車線数の減少などを理由に、安全性や円滑性確保を誘導するため
情報引用元:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 | e-Gov法令検索
導流帯の具体的な設置場所
導流帯は、国道や交通量の多い市街地など、主に道幅が広い道路でよく目にします。具体的には、以下の場所に設置されていることが多いです。
- 右折レーンや左折レーンの手前
- 交差点付近
- 幅が広く大きい道路の合流車線
このような場所に設置するのは、直進レーンから右折レーンへと、スムーズに車線変更をするためです。
たとえば以下の画像のように、右折したい車は導流帯に沿うように走ることで、自然に車線変更をすることができます。
導流帯(ゼブラゾーン)に入ってもいい?ルールを解説
こちらでは、導流帯(ゼブラゾーン)に入ってもいいのかどうか、走行時や駐停車のルールについて解説していきます。
走行は違反にはならない
導流帯(ゼブラゾーン)は法令上、特に立入禁止されていないので、導流帯の上を走行しても問題ありません。
そのため、特に違反点数が付いたり、反則金の対象になるようなことはないです。
ただし導流帯はあくまで、車の走行を誘導しやすいように設置されています。
そのため、導流帯の上を車が走行することは想定しておらず、警察では導流帯の上を走行しないよう指導しています。
駐停車は不可能
導流帯の駐停車に関しては、法令上禁止されていることはありません。ただし、導流帯のある場所は交通量の多い交差点付近に設置されています。
交差点付近は、駐停車禁止の場所に該当します。そのため、導流帯で駐停車をすると、道路交通法違反で違反点数と反則金の対象になると考えて良いでしょう。
導流帯(ゼブラゾーン)で起こりやすい事故と過失割合について
導流帯(ゼブラゾーン)で起こりやすい事故として、交差点手前での衝突事故が挙げられます。こちらでは、事故の原因や過失割合について解説していきます。
交差点手前|右折時の衝突事故
導流帯での事故の多くは、交差点手前の右折時に起こります。
下のイラストのように、導流帯の誘導に従い車線変更した車と、導流帯の上を直進してきた車との衝突事故です。
過失割合
上のイラストを例にすると、導流帯で起きた事故の過失割合は次の通りになります。
基本過失割合と、導流帯の走行による過失割合の修正後で比較してみました。
●直進してきたグレーの車:30%
●車線変更する緑の車:70%
●直進してきたグレーの車:30~50%
●車線変更する緑の車:50~70%
導流帯は、あくまで車の安全な走行を誘導する区間です。そのため、道路交通法では走行が禁止されているわけではありません。
しかし、「導流帯はむやみに走行するべきではない」という考えがあるので、導流帯走行のグレーの車には、10〜20%の過失が上乗せ修正されるケースもあります。
車線変更は余裕を持って
導流帯のある交差点では、右折時での衝突事故が起きやすいです。
そのため、交通量の多い場所では余裕を持ち、交差点の様子や車線変更をするレーンの車を確認してから車線変更をしましょう。
また、道路が濡れていると白線の上は滑りやすくなります。
雨の日や雪の日に導流帯の上を走行するとスリップ事故を起こしやすいので、注意が必要です。
導流帯と似た道路標示
導流帯に似た道路標示は、主に以下の4つがあります。
- 安全地帯または路上障害物接近
- 立ち入り禁止部分
- 停止禁止部分
- 安全地帯
道路標示によっては、導流帯と間違える可能性もあるので注意が必要です。
どういう道路標示なのかは、次項で紹介しているので参考にしてください。
安全地帯または路上障害物接近
前方に路上障害物が接近しているときに、知らせる道路標示です。「片側に避ける場合」と「両側に避ける場合」の2種類が存在します。
主に、高速道路やインターチェンジの合流場所に、設置されている場合が多いです。
立ち入り禁止部分
その名の通り、車が立ち入ることを禁止されている道路標示です。黄色の枠内には、車の走行・侵入・駐停車が禁止されています。
主に見通りの悪いカーブなど、事故が発生しやすい場所に設置されています。
停止禁止部分
これは、緊急車両の通行を確保するための道路標示です。そのためバスターミナルの前や、警察署・消防署の前に設置されています。
この道路標示の上を、車で走行することは許可されていますが、区画内に駐停車することはできません。
安全地帯
幅広い横断歩道の途中や、路面電車の停留所などにある道路標示です。ここでは車が侵入することが禁止されており、安全地帯に歩行者がいる場合は徐行運転をしなければいけません。
導流帯(ゼブラゾーン)についてのまとめ
- 導流帯の設置基準は「車両の安全、かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所」
- 導流帯の上を走行しても問題ないが、事故を起こすと過失割合が不利になる場合がある
- 安全地帯または路上障害物接近など、導流帯に似た道路標示もあるので見極めに注意を
導流帯は、交通量の多い交差点付近でスムーズに車線変更するための道しるべです。主に、直進から右折レーンへと車線変更する場所に設置されています。
最初から右折しようと導流帯の上を走行してくる車もいます。そのときに車線変更しようとすると、過失割合が大きくなるので気を付けてください。
この記事の監修者
![]()
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。