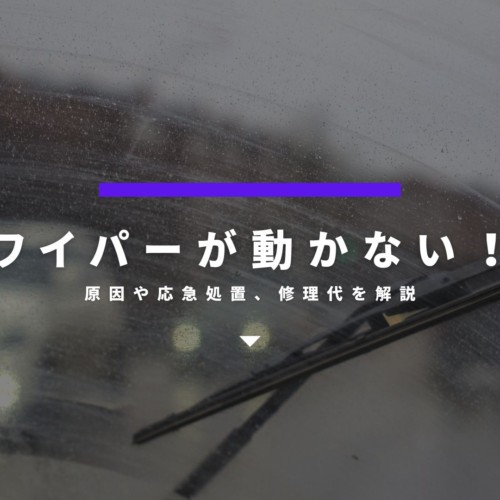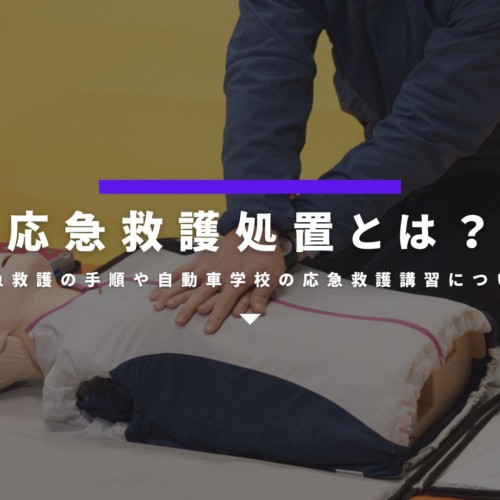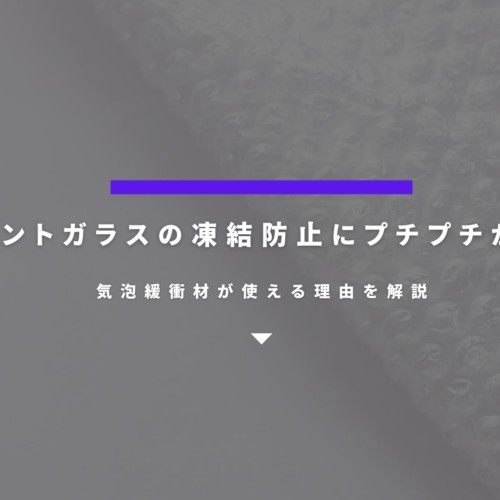車が冠水・水没したらエンジンはかかる?冠水車・水没車の症状や保険適用を解説
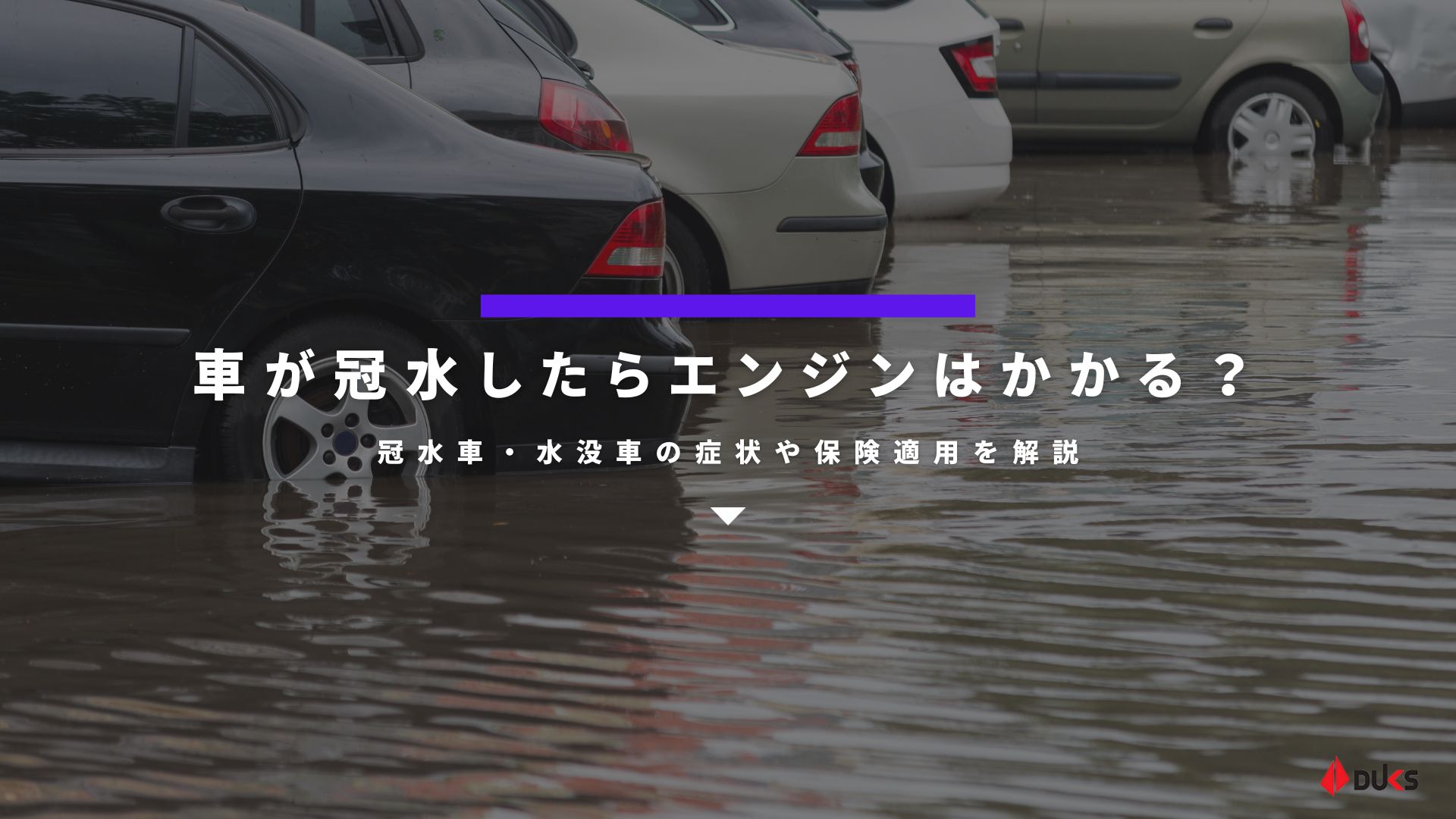
自然災害で車が大きな被害に遭うのは、主に台風や豪雨による冠水・浸水被害です。
日本は台風をはじめとする自然災害が多く発生するため、絶対に水害に遭わないとは言い切れません。
また、海沿いの近くに住んでいる場合、台風や地震の影響により、車が冠水するリスクが高くなります。
この記事では、車が冠水・水没してしまったときの対処法について解説していきます。

目次
冠水車と水没車の違いについて
水没車とは、水害によって浸水してしまった車のことです。フロアまで浸水していると、冠水車として扱われます。
水没車と呼ばれるのは、浸水具合がタイヤの半分より下までなのが一般的です。
そのため冠水車の方が浸水具合が大きく、水没車の方が浸水具合が低いと言えます。
冠水した道路には絶対に入らない
鉄則として、冠水している道路には絶対に入らないようにしてください。
こちらでは、どこまでの冠水なら走行できるのか、冠水した道路を走行する場合のリスクについて解説していきます。
車は水深30㎝でも冠水する可能性がある
「車は水深30㎝でも冠水する可能性がある」と、言われています。
水しぶきが高く上がる速度で走れば、水面よりも上の位置にまで影響が及ぶため、冠水した道路での走行はリスクが大きいです。
また、車種や道路の構造によっては、水たまりや冠水から受ける影響が違います。
コンパクトカーやセダンのような最低地上高の車両、SUVタイプのようにタイヤが大きく車高も高い車では、水たまりや冠水から受ける影響が違います。
高架下やガード下、立体交差点のアンダーパスなどは、周囲より道路の高さが低くなっているため、冠水の影響を受けやすいです。
冠水した道路を走行する場合のリスク
ゲリラ豪雨に遭うと、予想以上のスピードで冠水が進んでいきます。故障のほか、最悪の場合は車から抜け出せなくなり危険です。
また、水が引いて走行できる道路状況になっても、浸水による電気系統のショートなどが原因で車の部品が発火や爆発を起こしたり、ブレーキが効かなくなってしまったりします。
やむを得ず冠水した道路を走行しなければならない場合は、ATやCVTを低速域の設定にして、エンジン回転を高くした状態でゆっくり運転をしてください。
排気口の浸水をできるだけ防ぐほか、排気ガスの排出を促進させることで、車に対するリスクを低減させましょう。
車は冠水するとエンジンがかからない
車は、ある程度の浸水には対応できるような設計がされているものの、機械であるため水には弱い構造になっています。
ボルト穴やマフラーなどからエンジン内部に水が入ると、エンジンが壊れてしまう可能性が高いです(ウォーターハンマー)。
エンジンは、ガソリンと空気の混合気を圧縮し点火することで回転します。
圧縮することができない水がシリンダーに入ってしまうと、ピストンが圧縮しきれずピストンの動きを回転軸に伝えるコンロッドが曲がり、壊れてしまうのです。
また、エンジンルームや室内には電気系統の配線が集中しているため、水の侵入によって誤作動がおきたり、回路がショートしたりしてエンジンが停止してしまう確率が高くなります。
そして、洪水で道路にあふれた水には、下水道からの汚水が多く含まれています。
津波による冠水・浸水被害に遭った場合、海水に含まれる塩分によって金属部分の腐食が進んでしまい、車に大きなダメージを与えます。
車が冠水・水没したときの脱出方法
万が一、車が冠水してしまったり水没してしまったりした際は、落ち着いた行動を心がけてください。
焦って行動してしまうと、より命に危険が及ぶ可能性が高くなります。こちらでは、脱出方法について解説していきます。
脱出の手順
脱出の手順は以下の通りです。
冠水している道路で車が動かなくなってしまったら、速やかにシートベルトを外し、エンジンを切ってください。
水圧は非常に強い抵抗力があるため、水圧でドアが開かなくなってしまう場合があります。
具体的には、0.6mほどの水没でドアが開かなくなる可能性が高くなります。
車から脱出する際は、仰向けの状態になり、背中側から外へ脱出してください。
サイドガラスからの脱出方法
水位が窓まで到達していて窓が開かない場合は、脱出用のハンマーや先端のとがった丈夫なものでサイドガラスを割り、車から避難しましょう。
もし、ハンマーがなく窓を割ることができない場合、ヘッドレスト(頭をもたれ掛ける部分)を外し、柄の部分をサイドガラスと扉の間に差し込んで、力いっぱいガラスを割るようにしてください。
割れたガラスで怪我をしないよう、手や顔にタオルを巻いて行うのが理想的ですが、まずは命を最優先に動きましょう。
窓の高さまで水が到達していない場合、ドアからの脱出を試みようとしがちです。
しかし、ドアを開けてしまうと車内に大量の水が一気に流れ込んできてしまい、命に危険が及ぶ確率が高まってしまいます。
水位が窓まで及んでいなくても、サイドガラスからの脱出を図ってください。
避難時は冠水路の水深を測りながら
車から脱出した後、いきなり冠水路に出てしまうと、水深が思いのほか深かったり、マンホールの蓋が外れている箇所に足をついてしまう可能性があります。
まずは足先で水深を測りながらゆっくり足をつき、着地点の安全性を確かめてください。
冠水路を辿る際にも、水の底に何があるかわからないので、ゆっくり確認しながら足を進めてください。
冠水した車での走行はNG!冠水車、水没車の症状について

冠水や水没した車の走行は、基本的にはやめましょう。こちらでは、冠水した車や水没車の症状、トラブルについて解説していきます。
空気の取り入れ口の水詰まり
冠水・水没時にエンストが起こる原因の一つとして、吸気ダクトやエアクリーナーで水詰まりが起きてしまっていることが考えられます。
エンジンを動かすには、ガソリンの他に「空気」が非常に重要な役割を果たします。空気の取り入れ口が、冠水・浸水によって詰まってしまい、エンストを起こしてしまいます。
排気ガス詰まり
空気とガソリンによってエネルギーを作り出した後、エンジンから「排気ガス」と呼ばれるものが排出されます。
この排気ガスは通常、排気管やマフラーから排出されるのですが、この部分が冠水・浸水してしまったら排気ガスが溜まってしまい、エンストを起こします。
電気系統の異常
エンジンの周りにある電気機器のショートにより、エンジン制御システムが作動し、緊急停止が行われます。
感電事故を防ぐために、エンジンが作動しなくなります。
主なエンストの原因は上記で述べた、空気の入れ口の詰まりや排気ガスの詰まりになります。また、水位が高い場合は、電気機器のショートによりエンストが起きる可能性があります。
塩水による部品の劣化や腐食
冠水の原因は雨以外にも、海水によって車が浸水することがあります。たとえば、洪水や津波などで海水に車が浸かるケースです。
この場合は、海水に含まれる塩分によって車が錆びてしまうリスクがあります。海水に浸かると車が乾いた後も塩分は残るため、部品交換でも修復は困難です。
悪臭トラブル
冠水車を放置すると、カビや雑菌が発生して悪臭の元となります。
車を乾かしたとしても、床下などは乾かずに多湿状態が続くため、知らぬ間にカビや雑菌が徐々に繁殖していく可能性が高いです。
カビが原因で新たな故障箇所が増えることもあり、車の安全性も損なわれるリスクもあります。
冠水・水没した車の取り扱い方
冠水・水没してしまった車は、外見上問題がなさそうでも、エンジンのウォーターハンマーや電気系統のショートによる出火や爆発など車両火災の危険があります。
冠水や水没した車の取り扱い方については、以下の方法を参考にしてください。
- 自分でエンジンをかけない
- 速やかにJAFや自動車保険のロードサービス、自動車販売店、整備工場などに連絡する
- ハイブリッド車(HV)や電気自動車(EV)は高電圧のバッテリーを搭載しているので、できる限り触らない
水が引いた後に車を引き揚げる場合、保険会社やロードサービスなどのレッカー車を利用してください。
自分で運転して無理に動かそうとすると、感電事故を起こす恐れがあります。
車を引き上げた後は保険会社と相談してから、ディーラーや整備工場へ持ち込んでください。
破損の状況が軽ければ、修理した上で乗り続けることができますが、汚損や破損が酷い場合は売却、あるいは廃車扱いです。
加入している車両保険の条件で、扱いを相談しながら判断することになります。
車が冠水・水没した場合の保険適用について
車が冠水・水没した場合、保険が適用されるケースとされないケースについては、以下の通りになります。
保険が適用されるケース
車両保険が適用されるケースは、主に以下の通りです。
- 台風
- ゲリラ豪雨
- 洪水
- 高潮による被害
以上の被害の場合は、一般的な車両保険で補償されます。修理費用が保険の金額を超えるエンジンまで水没していて、修理が不可能な場合は全損扱いです。
ただし、洪水による損害で車両保険を使うと翌年1等級ダウンして、事故あり係数適用期間が1年加算されます。
保険が適用されないケース
車両保険が適用されないケースは、地震や噴火など「津波」による浸水です。
地震などによる津波で車が冠水しても、基本的には車両保険では補償されません。
ただし保険会社によっては、地震特約をオプションとして付けられる場合があります。
海岸沿いの近くに住んでいるなど、津波の被害が考えられる場合は、地震特約を付けるかどうか検討してみましょう。
車が冠水・水没したときの対応についてのまとめ
- 基本的には冠水した道路では走行をしない
- もしも車が冠水したら、シートベルトを外して速やかにエンジンを切り、サイドガラスから脱出する
- 冠水した車での走行はNGで、保険会社と車の取り扱いについて相談をする
車が冠水した後、水が引いた後に車を引き揚げる場合は、ロードサービスなどのレッカー車などを利用して運ぶようにしてください。
無理に動かしてしまうと、感電事故を起こす恐れがあるからです。

この記事の監修者
![]()
DUKS 受付窓口責任者
吹浦 翔太
年間84,000件のフロントガラストラブルに対応するDUKSグループで、受付窓口の責任者を務めています。
2008年から6年間、現場での実務経験を積み、現在は国内主要ディーラー各社からの修理依頼を中心に、状況の整理と修理方針の判断に携わっています。
保有資格は「JAGUフロントマスター」「ダックス事務検定2級」。
現場で培った知見をもとに、お客様にとって最善の修理をご案内します。