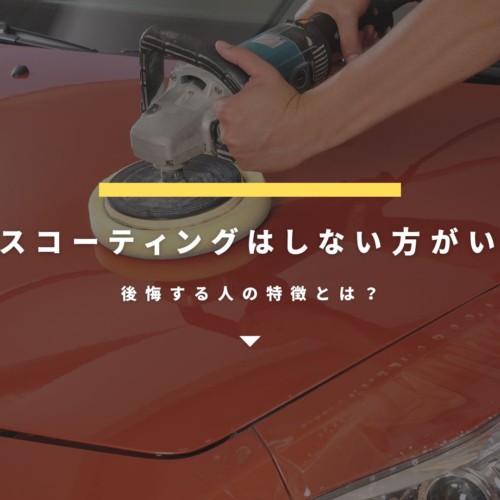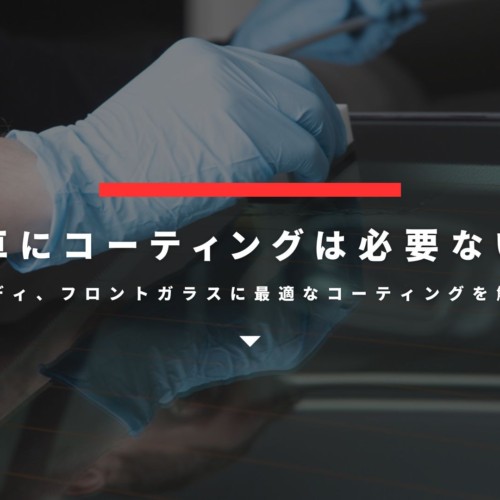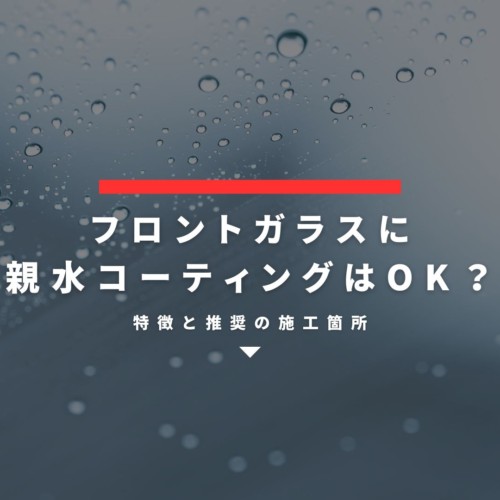【車の雪対策】冬に車に積んでおくべきもの、雪対策グッズを紹介

車の雪対策としては、サマータイヤからスタッドレスタイヤへの交換、タイヤチェーンなどのアイテムを車に積んでおくことが挙げられます。
雪による車のトラブルは、積雪の量によって左右されるわけではありません。滅多に積雪しない地域でも、突然雪が降って数cm積もるだけで事故が多発したり交通状況に大きな影響を及ぼしたりします。
この記事では車の雪対策について、車に積んでおくべきものや雪対策グッズ、事前に行うメンテナンスについて解説していきます。
目次
【車の雪対策】スタッドレスタイヤの交換は必須
雪道を運転する際に欠かせないアイテムの代表がスタッドレスタイヤです。
JAFが圧雪路と氷盤路で行った制動距離テストによると、スタッドレスとオールシーズンタイヤでは以下の差がありました。
| 圧雪路・時速40km/hでの制動距離テスト | 氷盤路・時速40km/hでの制動距離テスト | |
|---|---|---|
| スタッドレスタイヤ | 17.3m | 78.5m |
| オールシーズンタイヤ | 22.7m | 101.1m |
出典:JAF|走れても止まれない、雪道のノーマルタイヤ(JAFユーザーテスト)
スタッドレスタイヤですが、環境に応じて重視する性能も変わるため、以下のような例を参考に選んでみてください。
●路面凍結の多い地域:氷上性能
●降雪が少ない地域:寿命・耐摩耗性能・ドライ性能・ウェット性能・燃費性能
●積雪の多い地域:氷上性能・雪上性能
●年に数回降雪のある地域:ドライ性能・ウェット性能
スタッドレスタイヤの選び方については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
冬に車に積んでおくべきもの、雪対策グッズ6選
雪対策として、冬は車に積んでおくべきアイテムは次の6つです。
- タイヤチェーン
- フロントガラスカバー
- アイスクレーパーや解氷スプレー
- スノーブラシ
- スコップ
- フロアマット
タイヤチェーン
大雪警報が出ると、一定区間の道路や高速道路で「チェーン規制」が発令されることがあります。
チェーン規制が発令されると、スタッドレスタイヤだけでは対象区間の道路を走行することができません。そのため、冬は車にタイヤチェーンを積んでおいてください。
タイヤチェーンには、次の3種類があります。
- 金属タイヤチェーン
- 非金属タイヤチェーン(ゴム、ウレタン)
- 布製タイヤチェーン
性能が高いのは金属チェーンですが、振動や騒音が大きいため走行時の乗り心地が良くありません。
ゴムやウレタン製の非金属タイヤチェーンは、取り付けは簡単で振動や騒音が非金属チェーンよりも少ないです。しかし、コンパクトに折りたためないため、車に積む際に金属チェーンよりも場所をとります。
布製タイヤチェーンは耐久性が低いですが、取り付けは簡単で軽くて折りたたみやすく、車に積みやすいのが特徴です。
タイヤチェーンの効果については、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。
フロントガラスカバー
雪が降っても、フロントガラスカバーをかけておけば雪下ろしをするのが楽です。車に雪が積もると手で払うのが効果的ですが、手や指先が濡れたりかじかんだりします。
フロントガラスカバーをかけておけば、手でサッと雪を払ってカバーを外すだけなので、簡単に雪下ろしできます。凍結防止と合わせて、冬はフロントガラスカバーをかけておくのがおすすめです。
アイススクレーパーや解氷剤
アイススクレーパーとは、凍結したガラスの表面に付着している雪や氷、霜などを削り取るヘラのようなものです。「アイスカッター」とも呼ばれています。
ただしアイススクレーパー単体で使用すると、雪や凍結を削るのにかなり時間がかかってしまいます。そのため、エアコンや解氷剤と併用するようにしてください。
ちなみに金属製のアイススクレーパーを使用すると、ガラスを傷つけてしまう恐れがあります。プラスチック製やゴム製のものを、使うようにしましょう。
スノーブラシ
車に積もった雪を、手早く簡単に払い落とすブラシです。フロントガラスは、カバーをかけておけばすぐに雪下ろしができますが、それ以外の部分は手で払いながらスノーブラシも使用しましょう。
スノーブラシには、伸縮タイプやブラシ部分が回転するタイプなど、各メーカーから色んな種類のブラシが発売されています。
スコップ
車の周辺に積もった雪をどけるために、スコップも車に積んでおきましょう。駐車スペースの除雪はもちろん、タイヤがスタックしてしまった場合に役立ちます。
フロアマット
雪が車内に入ると運転席や助手席、後部座席のフロアが水浸しになるので、フロアマットは敷いておきましょう。雪でフロアが濡れてしまうのを防げます。
車の雪対策として、事前に行うメンテナンス
車の雪対策として、事前に行っておくと良いメンテナンスは、以下の4つです。
- フロントガラスのコーティング
- ウィンドウウォッシャー液の濃度を上げる
- スノーワイパーに交換しておく
- バッテリーの液量や電圧などを確認する
フロントガラスのコーティング
雪が本格的に降り出す前に、カーコーティングを再度しっかり行っておきましょう。特にフロントガラスは念入りに行ってください。
フロントガラスに撥水加工を施しておけば、雨や雪の日に視界が確保できるだけではなく、ガラスの凍結防止にも繋がります。
撥水剤も市販で多く取り扱われているので、できるだけ早めに対策を講じておくことができます。
ウィンドウウォッシャー液の濃度を上げる
ウィンドウウォッシャー液の濃度を上げておくべき理由は、液の凍結予防に繋がるからです。
通常通りのままの濃度にしてしまうと、ウォッシャー液を出した瞬間に凍結してしまう恐れがあります。視界が悪くなり、事故に繋がってしまう危険性も出てきてしまうので、ウォッシャー液の濃度は高くしておいてください。
また合わせて、冷却水(クーラント)の濃度も上げておきましょう。こちらも凍結予防のためです。冷却水が凍結してしまうと、最悪の場合、エンジンの交換をしなければならない事態になってしまうこともあります。出来るだけ交換をするか補充を行うようにしてください。
※冷却水の濃度が高いまま暖かい季節を迎えてしまうと、オーバーヒートを起こしてしまうことがあります。雪の季節が過ぎたら、早めに元の濃度に戻しましょう!
スノーワイパーに交換しておく
夏用ワイパーはワイパーの骨組み部分(ブレードと呼ばれています)が、金属で構成されています。雨や風には強いのですが、凍結には弱いのが特徴です。
その点、スノーワイパーはこのブレード部分がゴムで覆われているため、雪が降っても凍結せずに使用することができます。雪道運転時の安全を確保するためにも、冬が始まる前にスノーワイパーに交換しておきましょう。
バッテリーの液量や電圧などを確認する
冬は、車のバッテリーが上がりやすくなります。極度の低温下に車を置いておくと、バッテリーの性能は低下してしまいます。雪が降って厳しい寒さがやってくる前に、バッテリーの液量や電圧、性能をくまなくチェックしておきましょう。
また、経年劣化による性能の低下が起きる場合も考えられるので、出来るだけ万全な状態で冬を迎えられるようにしてください。
車の雪下ろし方法
車の雪下ろしをする際は、スノーブラシを使いましょう。スノーブラシを使い、次の順番で車から雪を落としてください。
雪下ろしをする際のポイントは、雪を車の左右に落とすようにすることです。車の前に雪を落とすと、車を動かすときに雪をどかす必要があり二度手間になります。
車の前に雪が積もっている場合は、車を出すための通り道を、スコップ等で作り出してから雪下ろしをしてください。
車の雪下ろしについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。
雪対策としてワイパーを立てるのはOK?NG?
雪の日は対策として、ワイパーを立てておいてください。ワイパーを立てておく理由は、次の3つです。
- 凍結によってワイパーがフロントガラスに貼り付くのを防ぐため
- ワイパー故障のリスクを低減させるため
- 雪深い日や地域では特に、車の目印にもなる
雪が降る寒い日は、ワイパーゴムが凍ってしまう可能性があります。寝かしたままワイパーが凍結すると、フロントガラスに張り付いてしまいます。
その状態で無理に動かそうとすると、ワイパーゴムが剥がれたり、ワイパーブレードが変形したりする可能性があり危険です。
また降雪時に車が雪に埋もれてしまった場合、雪の重さによりワイパーが破損する可能性があります。
そして自分の車を特定するために、ワイパーで判別するための手段となる場合もありますので、事前にワイパーを立てておいた方が良いです。
注意点としては、強風や暴風が吹いていたり、落雪の危険性があったりする場合は、ワイパーが壊れる危険性があります。それらの条件がある場合は、ワイパーを立てるのはやめましょう。
雪の日にワイパーを立てておく理由については、以下の記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。
降雪地帯を走行する際の注意点
積雪している道路や凍結している道路を走行する際は、以下の点を必ず守ってください。
- 車間距離を普段よりも長め(2倍以上)にとる
- カーブを曲がる際は十分に減速する
- ブレーキは早めにゆっくりと踏む
- アクセルはゆっくりと踏む
- ホワイトアウトが起きたらすぐに退避する
車間距離を普段よりも長め(2倍以上)にとる
雪道では、雪がタイヤに影響を及ぼし、ハンドル操作がスムーズにいかなくなることが多くなります。
道路が乾燥している時期と同じ感覚で走ってしまうと、先行車の減速や停止に対応しきれなくなり、事故に繋がってしまうことがあります。冬季の走行時は、車間距離を長く取ることを意識してください。
カーブを曲がる際は十分に減速する
交差点や曲がり角などでは十分な減速をしてください。多くの車が行き交う交差点では、タイヤが路面の凍結部分を磨いている「ミラーバーン」状態になっているほか、雪を踏み固めたことによって大変滑りやすくなっています。
エンジンブレーキを使って十分な減速をし、先行車・後続車と歩行者に細心の注意を払ってください。
ブレーキは早めにゆっくりと踏む
雪道での走行は、ブレーキ操作を慎重に行ってください。進行方向の危険を予測し、早めにブレーキングを行いましょう。
ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)が搭載されている車種も多くなりましたが、急ブレーキをかけた経験があまりないドライバーはABSの作動に反応しきれず、ブレーキから足を離してしまうことも多いようです。
車がスリップしてしまうとハンドル操作のみでの対処は困難を極めます。車体を元に戻せなくなり、大きな事故に繋がってしまうことも多くあります。そのため、ABSの反動にあらかじめ慣れておく練習をしておきましょう。
アクセルはゆっくりと踏む
アクセルを急に踏むと、発進する際にタイヤが雪に埋もれてしまう「スタック」という現象が起きることがあります。セカンドギアに切り替え、アクセルをゆっくり踏んで発進するようにしてください。
ホワイトアウトが起きたらすぐに退避する
吹雪や大雪によってホワイトアウトが起きると、走行時の視界が著しく遮られ、安全性が十分に確保できなくなってしまいます。
そのまま無理に運転を続けてしまうと大事故につながりかねないので、すみやかに安全な場所へ車を止め、しばらく様子を見てください。
路肩や交差点付近への停車は追突事故のリスクが高くなります。徐行しながら駐車場や待避所、非常駐車帯を探し、活用するようにしてください。
車の雪対策についてのまとめ
- 本格的な冬になる前に、サマータイヤからスタッドレスタイヤへの交換は必須
- 雪対策として車に積んでおくものは、タイヤチェーンやフロントガラスカバーなど
- 雪対策としてできるメンテナンスは、事前にしっかりと行う
本格的に雪が降る前に、できる準備はたくさんあります。雪が降ると、普段走り慣れた道でも危険に変わることがあります。普段以上の安全運転を心がけるためにも、車の状態を万全にしてから冬を迎えましょう。
この記事の監修者
![]()
DUKS 受付窓口責任者
吹浦 翔太
年間84,000件のフロントガラストラブルに対応するDUKSグループで、受付窓口の責任者を務めています。
2008年から6年間、現場での実務経験を積み、現在は国内主要ディーラー各社からの修理依頼を中心に、状況の整理と修理方針の判断に携わっています。
保有資格は「JAGUフロントマスター」「ダックス事務検定2級」。
現場で培った知見をもとに、お客様にとって最善の修理をご案内します。